PMS(月経前症候群)とは?症状・原因・対処法をわかりやすく解説
2025年 11月 15日 土曜日

月経前になると、気分が落ち込んだり、体がだるくなったりすることはありませんか?
それは「PMS(月経前症候群)」の可能性があります。
PMSは、月経の数日前から始まる心身の不調で、20〜40代の女性の多くが悩まされている症状です。
イライラや不安感、頭痛やむくみなど、その症状は人によってさまざま。日常生活に支障をきたすこともあるため、正しい知識と対処法を知っておくことが大切です。
本記事では、PMSの代表的な症状から原因、セルフケアの方法、医療的な治療法までをわかりやすく解説します。
毎月の不調と上手に付き合うために、ぜひ参考にしてください。
PMS(月経前症候群)とは?

PMS(月経前症候群)とは、月経の3〜10日前から始まる心身の不調のことです。
月経が始まるとともに症状が軽減または消失するのが特徴で、20〜40代の女性の約8割が何らかの症状を経験しているとされています。
PMSは多くの女性が悩む症状ですが、正しい知識を持つことで症状の緩和や予防につながります。
PMSの代表的な症状

PMSの症状は人によって異なりますが、大きく「精神的な症状」と「身体的な症状」に分けられます。
まずはそれぞれの特徴を理解することが、適切な対処への第一歩です。
精神的な症状
PMSでは、心の不調が顕著に現れることがあります。以下のような症状が代表的です。
- 理由もなくイライラする
- 気分が落ち込みやすくなる
- 不安感が強くなる
- 集中力が低下する
- 無気力になる
これらの症状は、ホルモンの変動によって脳内の神経伝達物質が影響を受けることで起こると考えられています。
仕事や家庭での人間関係に支障をきたすこともあるため、早めの対処が重要です。
身体的な症状
精神面だけでなく、身体にもさまざまな不調が現れます。
代表的な症状は次のとおりです。
- 頭痛や腹痛
- 肩こりや腰痛
- 乳房の張りや痛み
- むくみや肌荒れ
- 強い眠気や不眠
これらの症状は、ホルモンバランスの乱れや血流の変化によって引き起こされることが多く、日常生活の質を低下させる要因となります。
PMSの原因とメカニズム

PMS(月経前症候群)の原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
特にホルモンの変動と生活習慣の影響は、症状の出方に大きく関係しています。
ホルモンバランスの変化
PMSの原因の一つ主な原因は、月経周期に伴う女性ホルモンの変動です。
特に黄体期に分泌されるプロゲステロンが、脳内の神経伝達物質に影響を与えることで、気分や体調に変化をもたらします。
このホルモンの変化により、感情の起伏が激しくなったり、身体に不調が現れます。
ストレスや生活習慣の影響
ホルモンだけでなく、日々の生活習慣もPMSに大きく関係しています。
以下のような要因が症状を悪化させることがあります。
- 睡眠不足
- 偏った食生活
- 過度なストレス
- 几帳面で完璧主義な性格
- 甘いものやアルコールの過剰摂取
これらの要因は、ホルモンの働きを乱すだけでなく、自律神経にも影響を与えるため、PMSの症状を悪化させる可能性があります。
PMSのセルフケアと生活改善
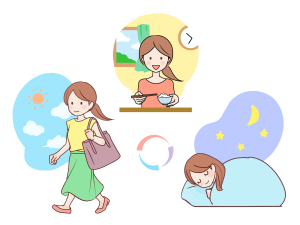
PMSの症状を軽減するためには、日常生活の中でできるセルフケアが非常に重要です。
特別な治療を受けなくても、生活習慣を整えることで症状が和らぐケースも多くあります。
食事・栄養面での対策
食事はホルモンバランスを整える鍵となります。
以下の栄養素を意識して摂取しましょう。
- ビタミンB6(バナナ、鶏肉、マグロなど)
- マグネシウム(ナッツ類、豆類、海藻など)
- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草など)
これらの栄養素は、神経の安定や血流改善に役立ちます。
反対に、カフェインやアルコールは症状を悪化させる可能性があるため、控えることが望ましいです。
運動・睡眠・ストレスケア
生活習慣の見直しも重要です。
以下のような取り組みが効果的です。
- 軽い運動やストレッチ
- 質の高い睡眠の確保
- アロマや瞑想によるリラックス
これらの習慣は、自律神経を整え、ホルモンの働きをサポートします。
特に、就寝前のスマホ使用を控えることで、睡眠の質が向上し、PMSの症状緩和につながります。
PMSに効果的な治療法と薬

セルフケアだけでは改善が難しい場合、医療機関での治療や薬の使用を検討することが有効です。
症状の程度に応じて、適切な方法を選ぶことが大切です。
低用量ピルの活用
低用量ピルは、ホルモンバランスを安定させることでPMSの症状を緩和します。
避妊目的だけでなく、子宮内膜症や月経困難症の治療にも用いられており、産婦人科で処方されることが一般的です。
副作用や体質に応じた選択が必要なため、医師との相談が欠かせません。
漢方薬による体質改善
漢方薬は、体質に合わせて処方されるため、根本的な改善を目指す方に適しています。
代表的な処方には以下があります。
- 当帰芍薬散(冷え性・貧血傾向の方に)
- 加味逍遥散(ストレスや不安感が強い方に)
漢方は即効性よりも継続的な体質改善を目的とするため、長期的な視点で取り入れることが大切です。
市販薬(OTC医薬品)とハーブ療法
病院に行くのが難しい方には、市販薬やハーブ製品も選択肢となります。
代表的なものは以下の通りです。
- 鎮痛剤(イブプロフェンなど)
- チェストベリー配合のPMS専用サプリ
これらはドラッグストアで手軽に購入でき、症状の軽減に役立ちます。
ただし、体質や副作用に注意し、薬剤師に相談することをおすすめします。
まとめ
PMSは多くの女性が経験する身近な症状ですが、正しい知識と対処法を知ることで、症状を軽減することが可能です。
まずは自分の症状を把握し、生活習慣の見直しやセルフケアを取り入れてみましょう。
それでも改善が難しい場合は、医師や薬剤師に相談することで、より適切な治療法を見つけることができます。
無理をせず、自分の体と向き合いながら、毎月の不調と上手に向き合いましょう。
「未経験から医療業界へ!EPファーマラインで新しいキャリアを!」 詳細はこちら▼
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム.


