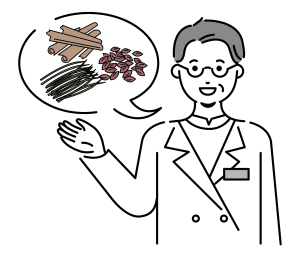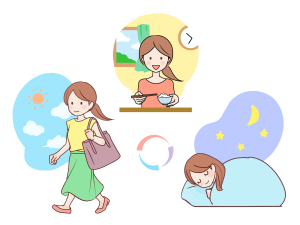ノロウイルスの症状・対策・患者指導ポイント|現場で使える説明例つき
2026年 2月 16日 月曜日
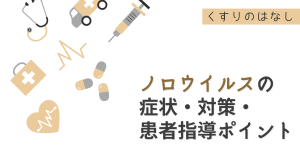
ノロウイルスは、家庭や職場で一気に広がりやすい感染症です。
理由は、感染後24〜48時間で嘔吐・下痢が急に起こり、トイレやドアノブなどを介してうつりやすいからです。
本記事では、症状の目安と受診のサイン、アルコールだけに頼らない手洗い・消毒・吐物処理の具体策、薬剤師がそのまま使える説明例まで、忙しい現場でも迷わないよう要点を整理しました。
ノロウイルスとは?どんな症状が出る?

ノロウイルスは、お腹の調子を崩すウイルスの代表格で、特に冬に流行しやすいことで知られています。
手や食べ物などを通じて体に入ると、腸の中で増えて、吐き気や下痢などを起こします。
症状が出るまでの時間(潜伏期間)とよくある症状
感染してから症状が出るまでの時間は、一般的に24~48時間です。
主な症状は次のとおりです。
- 吐き気、嘔吐
- 下痢
- お腹の痛み
- 発熱
多くの場合、症状は1~2日ほど続いたあとに回復し、後に引くことは基本的にありません。
どこでうつる?感染の広がり方
ノロウイルスは感染力が強く、家庭内や施設内で二次感染が起こりやすい点が注意点です。
感染が広がる主な経路としては、次のようなケースが多く見られます。
- トイレのあとなどに、手に付いたウイルスが口に入ってうつる
- 感染者が調理した料理を食べてうつる
- 牡蠣などの二枚貝を生や加熱不足で食べてうつる
- 嘔吐物が乾いて舞い上がったものを吸い込みうつる
ノロウイルスの対策方法

ノロウイルス対策のポイントは、①手洗いをしっかり行う、②食べ物はよく加熱する、③汚れた場所は正しく消毒する、の3つです。
➀手洗い
ノロウイルス対策で特に重要なのは、石けんと流水による手洗いです。
「アルコールで消毒しているから大丈夫」と感じる方もいますが、アルコール消毒は手洗いの代わりにはならないとされています(手洗いが難しい場合の補助としての位置づけ)。
また、手洗いの際は手のひらや手の甲だけでなく、指先や爪のまわりまで丁寧に洗うことが大切です。
<手洗いのタイミング>
- 食事の前
- トイレの後
- 調理の前
- おむつ交換や嘔吐物の片付け後
参考(出典):厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」 (閲覧日:2026年2月13日)
➁食べ物の対策
ノロウイルスは、加熱で感染力が弱まります。
「表面だけ温かい」では足りない場合がありますので、中心までしっかり熱を通しましょう。
特に牡蠣などの二枚貝は、中心部が85~90℃で90秒以上の加熱が望ましいとされています。
参考(出典):厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」 (閲覧日:2026年2月13日)
➂汚れた場所の消毒
ノロウイルスの対策では、床やドアノブなど、手が触れやすい場所を適切に消毒することが重要です。
このときに有効とされているのが、家庭用の「塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)」です。
ただし、消毒の効果や素材への影響は濃度によって変わるため、汚れの程度や場所に応じて濃度を使い分けることがポイントになります。
塩素系漂白剤の目安濃度
| 使う場所 | 目安の濃度 |
| 吐いたもの・便が付いた場所(床、おむつ等) | 0.1% |
| トイレの便座、ドアノブ、手すり、床など | 0.02% |
参考(出典): 広島市「消毒液の作り方と使用上の注意(次亜塩素酸ナトリウム)」 (閲覧日:2026年2月13日)
塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)は刺激が強いため、手指など皮膚の消毒には使用できません。使用する際は、ゴム手袋を着用し、十分に換気しながら取り扱ってください。
使用後は、素材への影響を抑えるため、必要に応じて水拭きを行うとよいでしょう。
嘔吐物の片付け方法

ノロウイルスは、吐いたものや便の中にウイルスが多く含まれます。
乾くと舞い上がることがあり、片付け方が雑だと二次感染の原因になりやすいです。
次の手順を参考に、適切な処理を行いましょう。
- 換気(窓を開ける、空気の流れを作る)
- 手袋・マスク・エプロンを着ける(使い捨てが理想)
- ペーパータオル等で、外から内へ静かに拭き取る
- 使ったものはビニール袋に入れて密閉して捨てる
- 汚れた周囲は、塩素系消毒液で浸すように拭く
- 片付け後は、必ず石けんと流水で手洗い
参考(出典):目黒区「家庭でできるノロウイルスの消毒方法」(閲覧日:2026年2月13日)
薬剤師目線での患者指導

ノロウイルスによる吐き気や下痢の症状があるものの、医療機関を受診すべきか判断に迷って薬剤師に相談される患者もいます。
薬剤師として、自宅での過ごし方や気を付けるべきポイントを、できるだけ分かりやすく伝えましょう。
脱水を防ぐ声かけを最優先に
ノロウイルスは特効薬がなく、基本は水分と栄養の補給をしながら回復を待つ形になります。
特に、乳幼児や高齢者は脱水になりやすく、脱水がひどい場合は点滴が必要になることもあります。
伝え方
- 「つらい時ほど、少しずつでいいので水分を取ってくださいね。」
- 「お子さんやご高齢の方は、脱水が心配なので、無理せず早めに医療機関に相談してくださいね。」
「下痢止め、飲んだ方がいい?」と聞かれたら
厚生労働省の見解では、下痢止めは回復を遅らせる場合があるため、使用しないことが望ましいとされています。
下痢を早く止めたいというお気持ちに共感しつつ、早期回復のためにも使用を避けるように伝えましょう。
伝え方
- 「下痢止めは、体の回復を遅らせることがあるので、まずは水分補給を優先しましょう。」
参考(出典):厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」 (閲覧日:2026年2月13日)
家族にうつさない“生活のコツ”をセットで伝える
ノロウイルスは、家庭内で広がりやすいので、患者さん本人だけでなく「家族を守る」視点が大事です。
家族がよく触れる箇所の消毒方法や嘔吐してしまったときの処理方法などを伝えてください。
伝え方
- 「ご家族に感染が広がらないように、全員で手洗いを徹底してください。」
- 「ドアノブやトイレなど、よく触る場所は塩素系漂白剤で消毒してください。」
まとめ
ノロウイルスは、感染から24~48時間ほどで嘔吐や下痢、腹痛などの症状が現れやすく、多くは1~2日程度で回復に向かいます。
一方で、家庭内や施設内で広がりやすいため、日頃からの手洗いの徹底と、食材の十分な加熱、吐いたもの・便の適切な処理がとても大切です。
このような感染症対応の場面では、「相手の不安に寄り添いながら、必要な情報を整理して分かりやすく伝える力」が、患者さんの安心と適切な行動につながります
EPファーマラインでは、メディカルコミュニケーターとして製薬企業の「くすり相談」窓口を担い、全国の医療従事者だけでなく患者様からの問い合わせにも対応し、医療を支える仕事に携わっていただきます。
現場で培った知識とコミュニケーション力をより広い範囲の患者さんの支援のために活かしてみませんか。
ご興味を持っていただけた方は、採用サイトで仕事内容や働き方をぜひご確認ください。
「未経験から医療業界へ!EPファーマラインで新しいキャリアを!」 詳細はこちら▼
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: 症状・病気