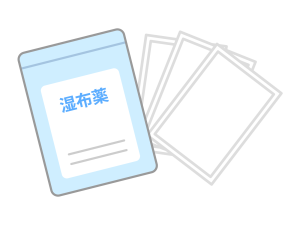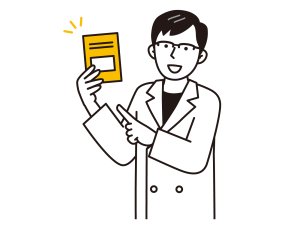ステロイドについてのお話し
2022年 10月 15日 土曜日
「ステロイド薬」とよく聞きますが、どのようなお薬かご存知でしょうか。
今回はステロイドの中でも、ドラッグストアなどでも市販されている「ステロイド外用薬」についてのお話です。
まず、ステロイドとは?
ステロイド骨格と呼ばれる構造を持つ化合物の総称です。
生体内ではホルモンとして働くものが知られており、副腎皮質から分泌される「副腎皮質ホルモン」や卵巣や精巣から分泌される「性ホルモン」などがあります。
さらに副腎皮質ホルモンには糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドに分類されます。
一般的によく言われる「ステロイド薬」はこの中でも糖質コルチコイドを元に作られたお薬で、炎症をおさえる作用があります。

ステロイド外用薬は作用の強さから5つのランクに分類されます。
弱い方から順に、「弱い(weak)」「普通(medium)」「強い(strong)」「とても強い(very strong)」「最も強い(strongest)」となります。
市販の外用薬では「弱い(weak)」「普通(medium)」「強い(strong)」に分類される成分が用いられます。かゆみ止めや抗菌薬の成分が配合されたものなども市販されていますので、ご自身で購入する際には症状によって使い分けが必要です。
使用量については一般的に「FTU」という単位がよく用いられます。
1FTUは大人の指先から第一関節まで乗せた量で、1FTU=約0.5gに相当します。
大人の手のひら2枚分に塗ることが可能と言われています。
部位によってだいたい何FTU使用するといった目安があります。
ステロイドは何か怖い…。と思う方も多いかもしれませんが、適切な薬剤を適切な使用方法・期間で使っていただければ、特に怖がるお薬ではありません。
逆に副作用を怖がって少ない量で使用してしまうと、十分に効果が得られない可能性があります。
使用量の目安は薬剤によって異なることもあるので、医師の指示に従ってください。
市販薬の場合は薬の説明書をしっかり読んで使用方法を守って下さい。
また長期に使用することも避けてください。
使用に不安がある場合は医師や薬剤師にご相談をお願いします。

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム