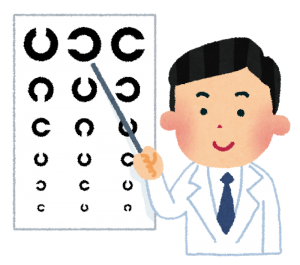お薬手帳のおはなし
2021年 9月 1日 水曜日
皆さんは、お薬手帳はお持ちでしょうか?
病院や薬局を利用すると必ずと言って良いほど聞かれると思います。
持っていない方、各施設で作ってしまい何冊も持っている方、持っているが必要性がいまいちわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はお薬手帳の役割についてお話しします。
医薬品には膨大な数の種類があります。さらに現在はジェネリック医薬品といって同じ成分、同じ効能なのに違う名称で販売されている薬も数多くあります。
複数の病院からそれぞれ薬を処方してもらうと、時々同じ成分の薬や、同じ効能の薬、さらには違う症状に対する薬同士で相性が悪く、一緒に飲んではいけない組み合わせなどが出てくることがあります。このような組み合わせをそのままにしていると、想定以上の効き目が現れたり、逆に効き目が現れなかったりといったことが起きてしまいます。
そうならないために、複数の病院で処方された薬をまとめて管理できるのがお薬手帳です。さらに薬の内容だけではなく、アレルギー歴や副作用歴を自分で書けるので、薬物治療をより安全に行うことができます。
また、お薬手帳は災害時にも役立ちます。災害時にはかかりつけの病院にいけるとも限りませんし、電気が止まるとカルテを見ることも困難です。各医療施設へ医薬品を安定供給することもできなくなるため、数少ない薬の中で代わりとなる薬を処方することになります。そんなときにも、お薬手帳があれば既往歴やいつも服用している薬を知ることができます。
災害が多い現代、いつ自分が被災者になるかわかりません。日常の薬剤管理のためだけでなく、災害の備えにもお薬手帳はとても重要なツールです。ぜひ1冊持って頂けたらと思います。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム