貧血のおはなし
2019年 6月 1日 土曜日
血液はからだの中を循環する、なくてはならないものです。
それでは、貧血とは、血液が足りなくなることをいうのでしょうか。
まずは血液についてです。血液は赤血球・白血球・血小板という細胞成分、血漿という液体部分から成り立っています。
赤血球:酸素の運搬をするヘモグロビンというタンパク質を含む
白血球:異物処理、細胞を貪食する(免疫機能)
血小板:止血作用
血漿:物質の運搬、体液の一定保持
そして貧血についてです。
「血液中の赤血球の減少、あるいは、赤血球中に含まれるヘモグロビン値が低下している状態」のことを指します。
お医者さんは、血液中の赤血球数、ヘモグロビン(赤血球の大部分を占める)の量、ヘマトクリット(血液中に占める赤血球の容積率)の値で貧血かを判定します。ヘモグロビン値が男性13.0g/dL未満、女性11.5g/dL未満を貧血の目安にしています。
中等度以上(ヘモグロビン値:9g/dL程度以下)の貧血や、急速な貧血では、以下のような多様な症状が起こります。
皮膚・粘膜蒼白、微熱、息切れ、倦怠感、頭痛、耳鳴り、めまい、失神、易疲労感
血液中のヘモグロビンが減ると、酸素を運搬する力が減り、身体全体は酸素不足になります。これを立て直すために、からだは心拍数や心拍出量を増大させ、呼吸数も増やしてしまいます。
貧血の原因には、赤血球の産生減少(造血幹細胞またはその分化障害、赤芽球の増殖成熟の障害)と赤血球消失量の増大(溶血や出血)が考えられます。
また、貧血の治療は不足した成分を補うことが基本です。
◎赤血球の成熟に必要な成分不足による貧血
- 鉄欠乏性貧血
[治療薬]鉄剤(経口・注射)
- 巨赤芽球性貧血
- ⇒ビタミンB12または葉酸の不足(DNA合成をとめてしまう)
・ビタミンB12欠乏性貧血(悪性貧血)
[治療薬]ビタミンB12製剤(注射)
・葉酸欠乏性貧血
[治療薬]葉酸(経口)
- 腎性貧血
- ⇒腎臓で産生され、赤芽球前駆細胞を分化や増殖するエリスロポエチンの不足
[治療薬]エリスロポエチン製剤
◎赤血球の産生障害による貧血
- 再生不良性貧血[治療薬]タンパク同化ステロイド:メナテトレノン
- 抗胸腺細胞グロブリン、骨髄移植
- ⇒造血幹細胞の異常
- 二次性貧血(悪性腫瘍・感染症・腎不全)
◎赤血球破壊の亢進による貧血
- 自己免疫性溶血性貧血[治療薬]糖質コルチコイド(ステロイド)、免疫抑制剤
- ⇒赤血球に自己抗体ができてしまう
貧血の多くは鉄欠乏性貧血です。この貧血は、食事からの摂取量では足らず、鉄剤を服用しなければなりません。ヘモグロビン値が基準に戻ったからと言って、すぐに治療を終了してしまうと再び貧血になってしまうおそれがあります。ゆっくりと治療を続けて回復を待ちましょう。
また、貧血の原因には消化管や婦人科領域に原因があるかもしれません。貧血かもしれない、と思ったら病院で原因を明らかにしましょう。
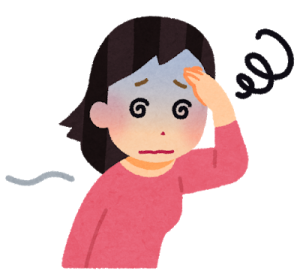
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム



