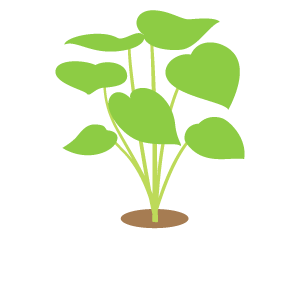セルフメディケーション税制について
2017年 6月 1日 木曜日
みなさんは『セルフメディケーション税制』という言葉を聞いたことがありますか。
『セルフメディケーション税制』は、2017年1月1日から始まった、新しい医療費控除制度です。
従来の医療費控除制度は、1年間に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合に、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されたりする制度です。セルフメディケーション税制では、治療のためにドラッグストアなどで購入したOTC医薬品(一般用医薬品)の代金もこの医療費控除制度の対象となります。従来の医療費控除制度は、1年間に合計10万円の医療費がかからなければ医療費控除に該当しなかったところ、今回の『セルフメディケーション税制』では、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用されます。
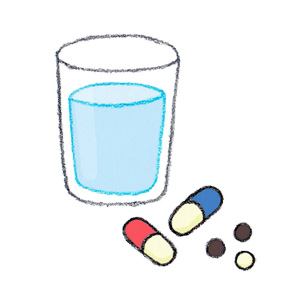
ただし、セルフメディケーション税制を利用するには、対象となる医薬品、対象となる人に条件があります。
《対象となる医薬品》
対象医薬品は約1,500品目あります。対象製品は厚生労働省のHPでご覧いただける他、製造メーカーの自主的な取り組みにより、パッケージに識別マークの印刷やシールが貼られています。医師の処方せんが必要な医療用医薬品から、OTC医薬品に転用された、いわゆるスイッチOTC医薬品と呼ばれるものが対象となっています。
《対象となる人》
所得税や住民税を納めている人で、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、②予防接種、③定期健康診断(事業主健診)、④健康診査、⑤がん検診のいずれかを受けている人です。
この制度を利用するためには、通常の確定申告に必要な書類の他、対象となるOTC医薬品を購入した際のレシート、定期健康診断を受けたことを証明する書類(領収書、結果通知書など)の提出が必要となります。レシートには、この制度の対象製品に★などの印と「セルフメディケーション税制対象」と記載があるので、レシートや領収書はこまめに保管するくせをつけると良いでしょう。

参)セルフメディケーション税制普及・啓発用チラシ(OTC医薬品協会HPより)、セルフメディケーション税制Q&A(厚生労働省)
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム