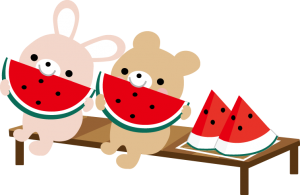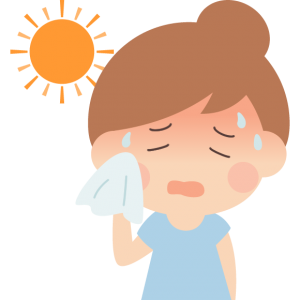日焼けのおはなし
2017年 7月 15日 土曜日
7月に入り、暑い日が続いていますが、日焼けが気になる季節だと思います。
そこで、今日は「日焼け」についてのおはなしをしたいと思います。
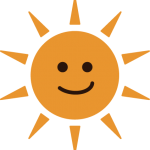
紫外線は、1年のうちでは6月から8月、1日のうちでは正午頃にもっとも強くなります。強い紫外線に長時間さらされると、皮膚が赤くなってヒリヒリ痛むことがあります。いわゆる日焼けという状態ですが、これは日光皮膚炎(紫外線皮膚炎)という炎症です。
主な症状としては、紫外線にあたった部分が赤くなり、ヒリヒリします。
ひどいときには皮膚のむくみや水ぶくれが現れることもあります。
症状には個人差がありますが、このような炎症症状は、強い紫外線に当たってから6~24時間後にもっとも強くなります。
日光皮膚炎になった場合には、まずは冷やすことが大切です。
熱っぽくヒリヒリしている部分に、冷たい濡れタオルを当てるなどしましょう。
ビニール袋に氷と水を入れ、タオルでくるんだものを使うのも良いです。この場合は必ずタオルでくるみ、皮膚に氷を直接当てないように注意が必要となります。
長時間強い紫外線に当たった場合は、皮膚の症状だけでなく、熱射病を起こしたり、発熱したり、脱水になってしまうこともあります。皮膚の炎症による全身の脱水を防ぐためにも、こまめな水分摂取も大切です。
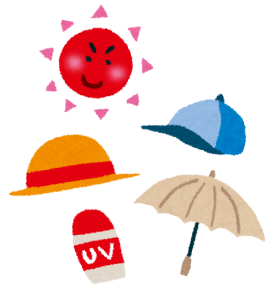
皮膚炎がひどい場合は早めに皮膚科を受診しましょう。
治療薬としては、炎症の程度に応じて、非ステロイド性抗炎症外用剤やステロイド外用剤などが用いられます。
炎症が治まった後にも、化粧水で皮膚に十分な水分補給をし、乳液やクリームなどで肌の保湿をすることも大切です。
また、帽子や服装の工夫で肌に直接日光をあてないようにしたり、日傘や日焼け止めも適切につかい、あらかじめ予防をすることもこころがけましょう。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム