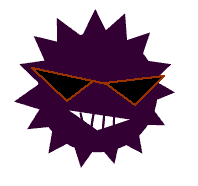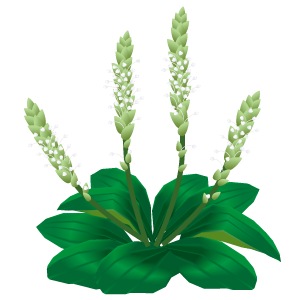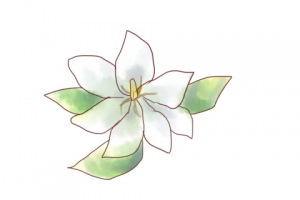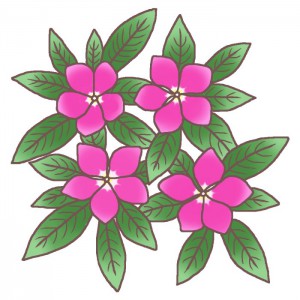麻酔薬を開発した人のはなし
2016年 8月 15日 月曜日
みなさんは華岡青洲(はなおか せいしゅう)をご存知ですか?
華岡青洲は和歌山県出身の外科医です。
麻酔薬を開発し、世界で初めて全身麻酔による乳がん手術を成功させました。
麻酔薬とは、「痛い」と感じる感覚を一時的に取り除くことができる薬です。
麻酔薬がなかったころは、患者は痛みを我慢しながら手術を受けるしかありませんでした。
華岡青洲は研究を重ねた結果「通仙散(つうせんさん)」を開発し、1804年に通仙散を使って世界初の全身麻酔による手術を成功させました。
通仙散の主な材料は植物の毒です。
「マンダラゲ(曼陀羅華)」(別名:チョウセンアサガオ)という植物を中心に、「トリカブト」など数種類の植物を調合して作られました。「マンダラゲ」には、人間の体をしびれさせる毒があります。その毒を利用して、痛みの感覚をなくすことで手術を行うことができました。
当時、乳がんは一度かかると治らない病気といわれ、華岡青洲も妹を乳がんで亡くしていました。そのため華岡青洲は「乳がんの手術を成功させたい」という思いが強かったようです。
今では、目の病気は眼科、骨折は整形外科というように病院の診療科は細かく分かれていますが、当時はそのような区別はありませんでした。華岡青洲はあらゆる病気や怪我を診察し治療や手術をおこない、たくさんの治療道具や手術道具を開発しました。麻酔薬の通仙散を使用した手術例は100種類を超えていたといわれてい ます。
ます。
華岡青洲は、たくさんの人たちを病気や怪我の苦しみから救った天才医師だったのです。
手術を受けるとき、麻酔薬がなかったら・・・と想像するだけでも怖いです。華岡青洲のような偉人のおかげで、わたしたちは安心して手術を受けることができるのですね。
参考:華岡青洲顕彰施設 青洲の里へようこそ!(http://seishu.sakura.ne.jp/)
製薬協のホームページ(http://www.jpma.or.jp/)
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム