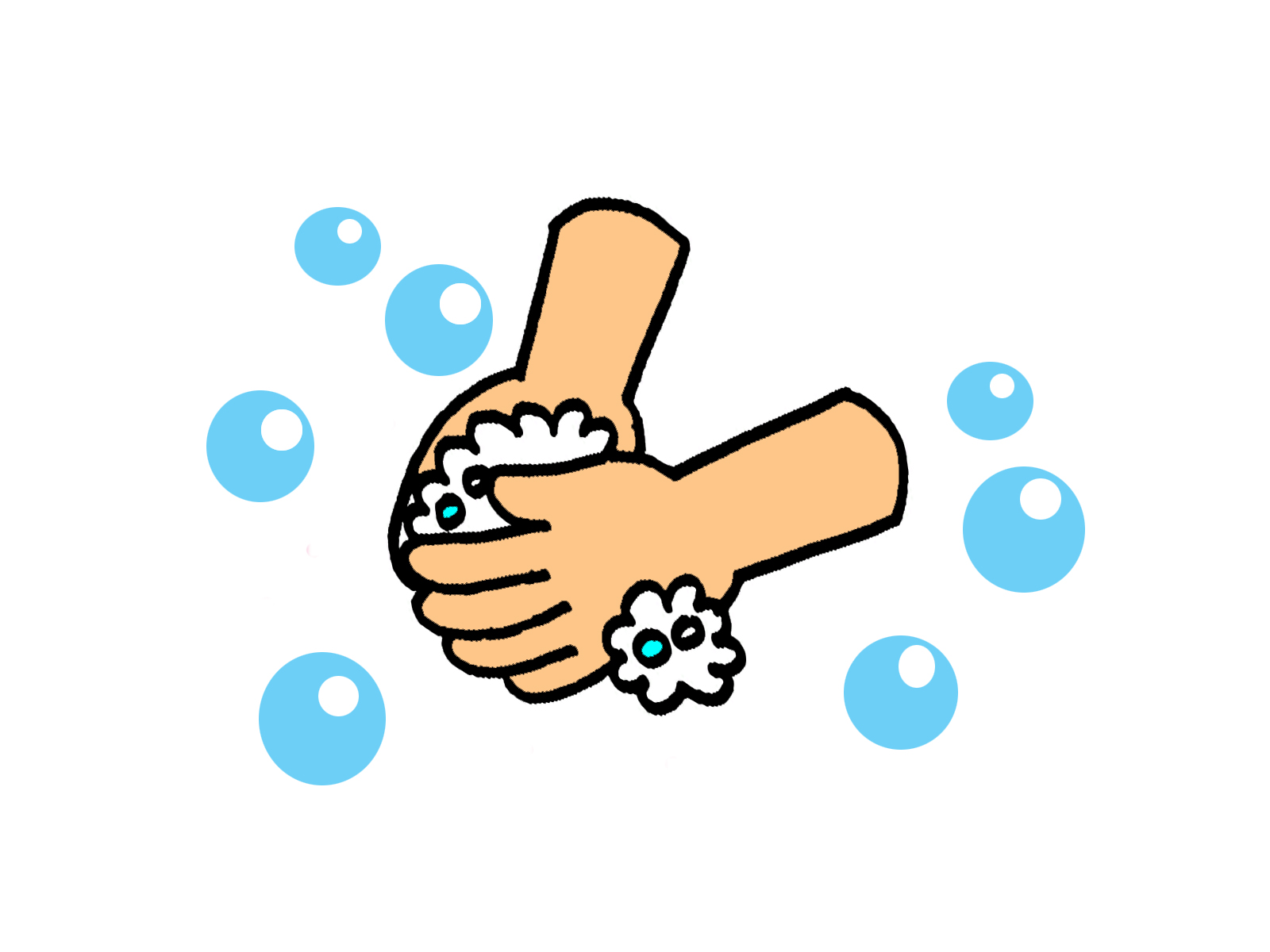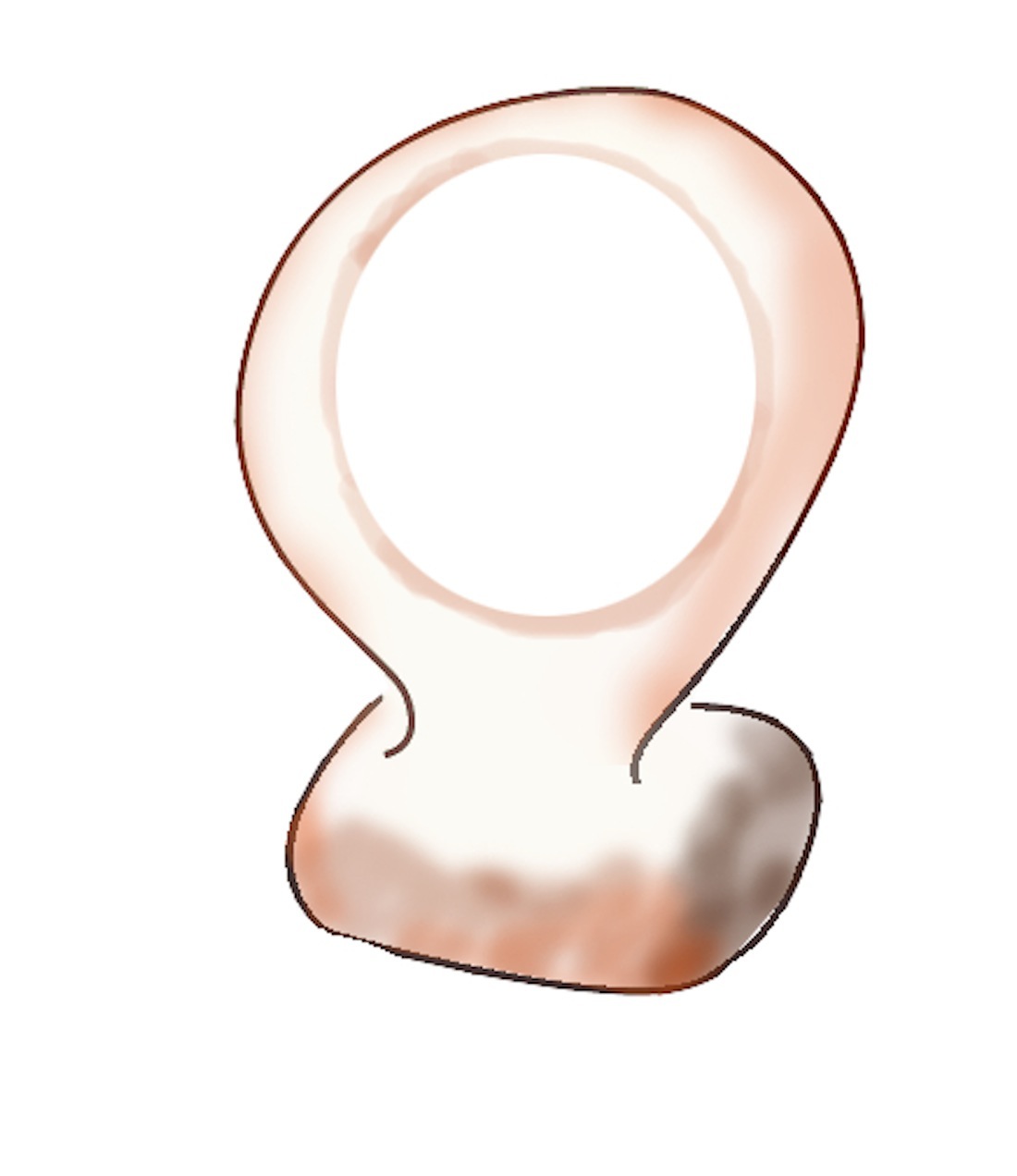アロマの力のはなし
2013年 2月 1日 金曜日
このブログを書いている今、私は何年かぶりに風邪を引いています![]()
もともと病院で勤めていましたが、病院で勤めている間は風邪1つ引かなかった私。
そんな私が風邪を引いてしまったのは、この職場にご縁を頂いて、ほっとして気が緩んだのが理由か、
それともあることを怠ったからか・・・。
病院に勤めている間は徹底して感染対策を行っていました。
もともとアロマが大好きなので、アロマを使って感染対策を行っていました。
最近では飲み会が続き、このアロマテラピーを怠っていたのが原因で風邪を引いちゃったのかも。
今回は私が実際に行っていた感染対策をご紹介します![]()
![]()
とっても簡単なので、皆様もご参考にされてはいかがでしょうか![]()
=======================================================
☆準備するもの
精油:殺菌、消毒作用のある精油を数滴
ティートリー、ラベンダー、ペパーミント、ローズマリー
(ペパーミントやローズマリーは集中力アップの作用もあり、勉強するときもおすすめ)
☆使い方
アロマランプなどを用いて芳香浴を行います。芳香浴とはお部屋全体に精油を充満させること。お部屋の広さに合わせて精油の量は調節してくださいね。アロマランプが無い場合はマグカップにお湯をいれたものに数滴、精油を入れたらOK。
また、風邪の症状が出始めたら、以下の精油で芳香浴を行うか、ハンカチに1滴垂らしたもの、ティッシュに1滴たらしたものをハンカチではさんだりしてもOK)を嗅ぐだけでも楽になります。ハンカチなら職場で咳き込んだ時なんかにすぐ取り出せて良いですよ。
精油 作用
サイプレス 咳を鎮める。
ユーカリ 鼻の炎症を抑える
ラベンダー 炎症を抑える
この感染対策をしてからほんと風邪知らずで、私もアロマのすごさに感動しています![]()
=======================================================
そもそも精油を使った方法がアロマテラピーとして体系化されたのは、1930年頃で、
フランス人によって命名されたこのセラピーは、もともとは医療的なものでした。
そのため、今でもヨーロッパの一部では精油を薬のように使っています。
アロマテラピーが日本にやって来た時には、美容やリラクゼーションとして受け入れられましたが、
1990年代に設立された、いくつかの専門的な団体の影響もあり、
アロマテラピーを医療分野で取り入れていこうという流れがでてきました。
そして現在では治療にアロマテラピーを活用する病院もあるようです。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム