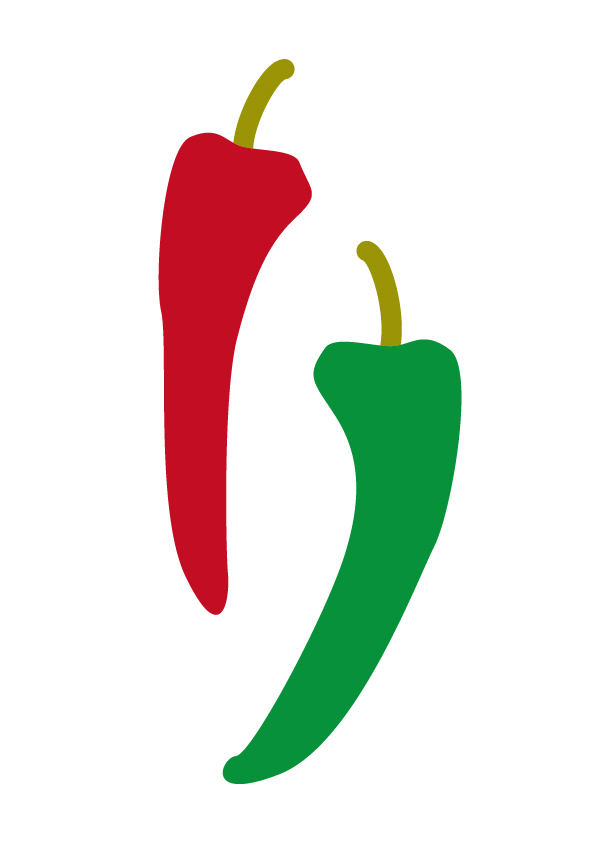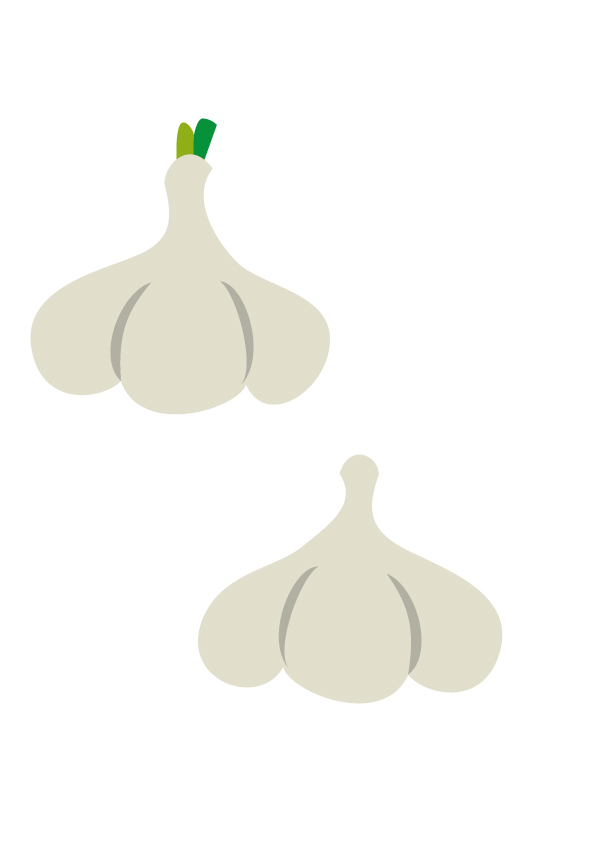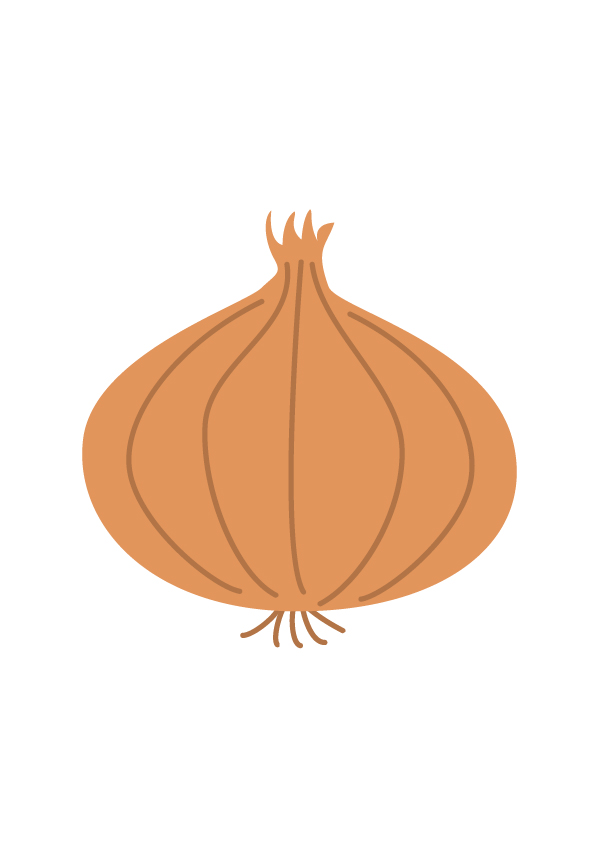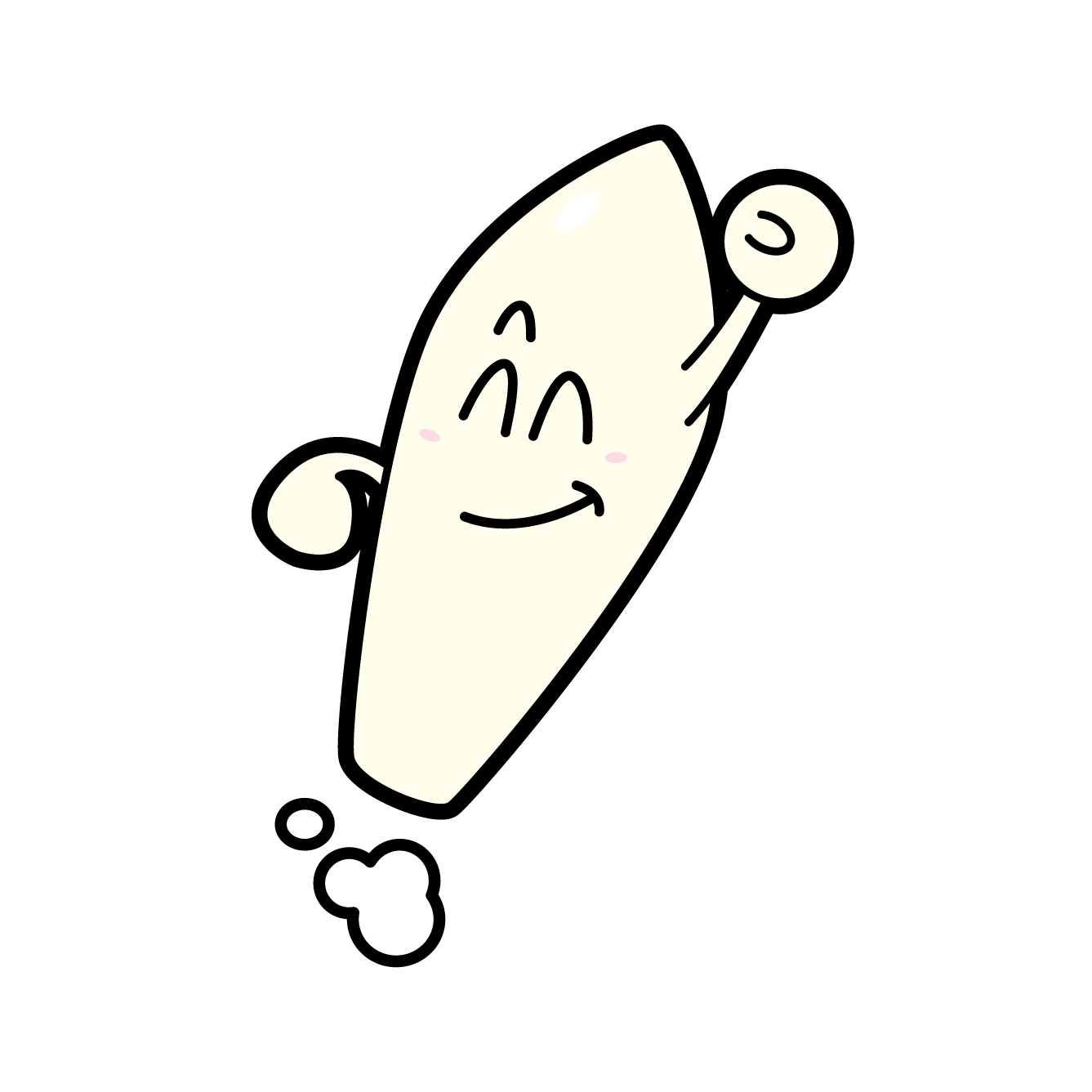食材には性質がある!?のはなし
2012年 12月 17日 月曜日
![]()
![]()
このところ、急激に寒くなりましたが、皆さん体調崩されていませんか![]()
多忙な年末年始を無事に乗り切るためにも、体調管理は大事ですよね。
その対策としては、冷えを取り除き、各器官の働きを高め、栄養を行き渡らせる必要があります。
特に冬はエネルギーを生み出す機能が低下するため、冷えや風邪が起こりやすくなります。
私も自覚症状のない【冷え性】(末端だけでなく内臓も冷えやすい体質)のため、気づくと胃の調子が悪かったりしています。
そんな時は自分でお灸をすることもありますし、ひどい時には鍼灸院に行ったりもします。
もちろん、ひどくならないように普段から食事の内容に気をつけています。
特に以下のものは注意しています。
・冷たいものは摂らない
・刺激物は控える
・旬の食材を温めて摂る
突然ですが、皆さん、食材には性質があるのをご存知でしょうか。
これは、中医学の理論に従った考え方なのですが、
食材や漢方薬には 『 熱 ・ 温 ・ 平 ・ 涼 ・ 寒 』(五性) の性質があります。
文字通り、冷えが気になる方は陽性(熱・温)の食材を摂ることが望ましいのです。
食材の例としては・・・
熱 : 唐辛子、山椒、胡椒、シナモンなど
温 : 生姜、紫蘇、ニンニク、ニラ、タマネギ、玄米、杏、蕪、棗など
ただし、ひとつの(熱・温性の)食材をまとめて大量に摂ると、一時的に体が熱くなり、
その反動が体の負担となる場合もあります。
お薬だけでなく、食材も摂り過ぎはいよくないですね。偏りも良くないですね。
なお、 『平』とは、冷やしすぎず、温め過ぎない穏やかな性質をもつ食材です。
体質によらないため、病後など体力が低下している時・もともと体力がない人には良いと言われています。
例としては・・・
平 : 黒ごま、小豆、大豆、りんご、牛乳、はちみつなど
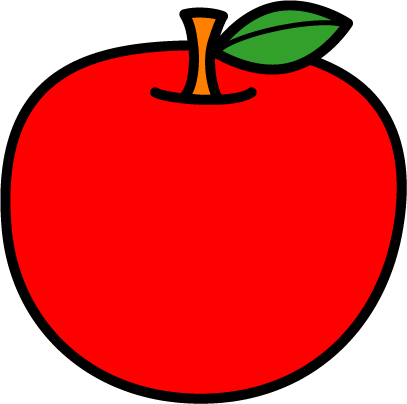

私は体調がいまいちの時は、りんごを焼いたり、煮たりして、性質を温として摂ります。
五性は加熱調理などによって、変わることがあるのです ほほぉ~
ほほぉ~
さらに、はちみつとシナモンをかけることで、温性をプラスし、体調回復を図ります。
サプリメントで栄養素を補給することは簡単ですが、
やはりバランスの良い食事から栄養素を摂取することが身体には一番です。
特に旬の食材には、その季節に必要な効果(性質)があるとも言われています。
忙しい時こそ、少しだけ 季節感を感じる食事
を心掛けると、心にも身体にも良いのではないでしょうか。
しかし、食べすぎは良くありませんので、ほどほどにしましょう。
それでは、皆さん、元気で年末年始と厳しい冬を乗り切りましょう![]()
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム