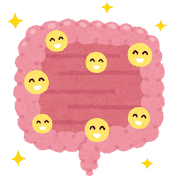一包化のおはなし
2023年 4月 15日 土曜日
複数のお薬を飲まれているみなさま、
お薬の管理について悩まれていることはございませんか?
本日は、「一包化(いっぽうか)」というものをご紹介したいと思います。
一包化とは…
同じタイミングで飲むお薬や、1回に複数個飲むお薬を1袋にまとめることです。
袋には、患者さんのご希望に沿って、飲むタイミング(朝食後など)、日付、患者さんのお名前、お薬の名前などを印字することができます。
ただし、一部のお薬において、湿気に弱い等の理由から一包化できないお薬もございますので、詳しくは薬剤師へご相談ください。
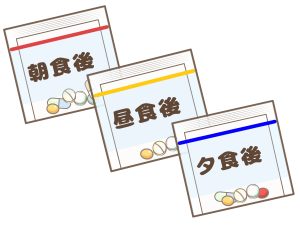
一包化をしてもらうには?
基本的には医師の指示が必要です。医師に相談する、もしくは薬局で薬剤師から医師へ確認をとってもらうようご相談ください。
複数の医療機関を受診していらっしゃる方は、他の医療機関でもらっているお薬もまとめて一包化することが可能ですので、相談してみてください。
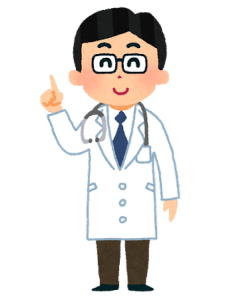
一包化の費用は?
保険適用となった場合のおおよその金額は、以下の通りです。
42日分以下の場合 : 7日分ごとに34点 (340円)
43日分以上の場合 : 一律240点 (2400円)
→保険適用されますので、1〜3割負担となります。
例)1割負担 28日分の一包化:340円×4週間×1割負担 →約140円
1割負担 56日分の一包化:2400円×1割負担 →約240円
なお、保険適用となる一般的な条件は以下の通りとなりますが、
詳しくは医師または薬剤師へご相談ください。
・お薬が2種類以上処方されており、
飲むタイミングが2つ以上(朝夕食後など)である
・お薬が3種類以上である

一包化のメリット
・お薬の飲み間違い、紛失を防ぐことができる
→お薬が1回分ずつ袋に入っており、飲むタイミングや日付を袋に印字することができるので、お薬の飲み間違いや紛失を防ぐことができます。
・お薬を1つずつシートから取り出さなくてよくなる
・介助者の負担が減る
→1袋分を本人に渡すだけであり、わかりやすく、手間が減ります。また、施設を利用されている方の場合、袋に氏名を印字することで他人のお薬との取り間違えを防ぐことができます。
一包化のデメリット
・費用がかかる
・お薬の追加や調整に時間がかかる
→お薬が変更となった場合、家に残っているお薬を薬局へ持って行き、再度調整してもらう必要があります。
・長期保管することができない
→お薬の使用期限は、お薬をシートに入れたまま保管した場合の期限となります。一包化をする際には、お薬をシートから取り出すため、使用期限が本来より短くなります。古くなってしまったお薬は、薬剤師と相談し服用しないようにしましょう。
・一包化するのに時間がかかり、待ち時間が長くなる
→FAXやアプリなどを用いて事前に薬局へ処方箋を送付しておく、薬局へ処方箋を渡してから買い物などの用事に出かけるなどをおすすめします!

お薬の管理方法には、お薬カレンダーなど、今回ご紹介した一包化以外の方法もございます。
お薬の管理に悩まれている方は、まずは医師または薬剤師へお気軽に相談してみてください。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム