「笑い」が薬になる?のおはなし
2022年 3月 1日 火曜日
突然ですが、皆さん「お笑い」はお好きですか?
お笑いの本場、大阪で興味深い試みが行われています。
大阪国際がんセンターにて平成29年5月より、「笑い」ががん患者さんの心身にどんな影響を与えるのか、という研究がスタートしました。
方法は・・・
40歳以上65歳未満の患者さん約60人に2週間に1回、芸人の漫才や落語を鑑賞してもらいました。計8回の公演をすべて見るグループと、半分だけのグループに分け、鑑賞の前後に血液検査やアンケートを実施し、笑いが免疫機能や患者さんの生活の質(QOL)に与える影響を比較しました。
結果は・・・
鑑賞前と比べ、血液検査では、免疫を高めてがんを抑える作用をもつタンパク質「IL-12B」(インターロイキン-12B)を出す能力が1.3倍になったことが確認されました。また「痛み」の症状も改善し、認知機能の向上もみられました。
今後は・・・
第2弾の研究が平成30年12月より実施中で、今後の結果が期待されています。
「気分が落ち込んでいたり体がしんどいなあと思っているとき、何かちょっとしたきっかけで笑うことで、気分が軽くなった、元気になった。」
という経験、皆さんもあるのではないでしょうか。
これが、「気のせい」ではなく科学的に証明されれば、すごいことですね。
今回の研究はがん患者さんが対象ですが、もっと広くとらえて、日常生活に「笑い」を取り入れることで、多くの人々が心も体も元気に過ごせるような社会になれば嬉しいですね。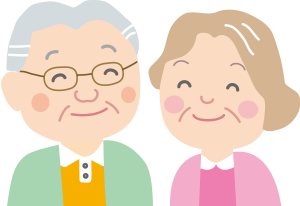
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム




