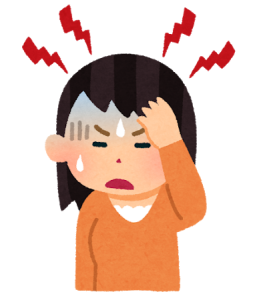漢方薬のおはなし
2021年 6月 1日 火曜日
今日は漢方薬についてのお話です。
現在病院にかかっていらっしゃる方も、そうでない方も漢方薬が市販で手に入りやすい環境となりました。
漢方薬の特徴や、西洋医学で使われる薬と漢方薬の違い、漢方薬の特徴について説明させていただきます。
漢方薬の最大の特徴は、同じ病気でも患者さんの体質によって使う薬が変わってくるということです。
言い換えると、患者さんの体質にあわせてオーダーメイドの医療、つまり、一人ひとりにあった医療を選択することが出来るということです。
今回は患者さんの体質を分類する方法の1つである「虚実」について、簡単に説明していきます。
虚実とは、基本的な体力や体格、病気に対する反応のことをいいます。
虚証の場合、体力が無く疲れやすい、抵抗力が弱い、胃腸が弱く下痢をしやすい、冷え症であるといった方が当てはまります。
実証の場合、体力・抵抗力があり、胃腸が丈夫でどちらかというと便秘気味、赤ら顔でのぼせるといった方が当てはまります。
雰囲気としては、虚証は細くてかよわい方、実証は力強くがっちりした体格の方となります。
虚実に着目して見てみると、風邪を引いた場合でも使う漢方は違ってきます。
元々体力のある実証タイプの方が風邪をひいた時は、葛根湯や麻黄湯がよく効きますが、体力のない虚証タイプの方が風邪をひいた時は、桂枝湯や香蘇散がよく効きます。
しかし、元々体力がある実証タイプの方が働きすぎなどで一時的に弱っている場合等は、実証タイプの方にでも、葛根湯ではなく、虚証タイプに使う桂枝湯が良く効く場合も有ります。
このように、同じ病気でもその人の体質によって使う漢方は違ってくるし、同じ人であってもその時の体調や状況でも違う漢方を選ぶことが出来ます。
ですので、漢方では虚証・実証の見分けを含めた、体質の見分けが重要となっています。
虚実以外にも様々な要因が考慮されます。迷われる場合には薬剤師さんに相談してみてはいかがでしょうか。
最後に、西洋医学と東洋医学の違いについてです。
現在の医療では、検査で異常がなければ病気ではなく治療の必要はないとみなされますが、ちょっと調子が良くない時、元気だけど体質を変えたいといった時にも漢方での治療の対象となります。
漢方を使った東洋医学の守備範囲は健康な方から重病な方までと、とても幅広いものであるため、色んな症状にうまく漢方を使っていただければと思います。

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム