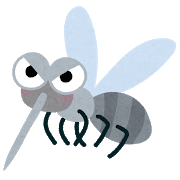糖尿病薬の意外な由来のおはなし
2020年 9月 1日 火曜日
皆様こんにちは。
突然ですが、皆様が普段何気に飲んでいるお薬って何をもとに生まれるかご存知でしょうか?
実は意外なところから、新しい薬が誕生することがあるのです!
今回私がお話するのは糖尿病の薬の意外な由来についてです。
糖尿病の薬はここ数年でめまぐるしい変化を遂げております。
現在多くの患者様を救っている多くの糖尿病薬は、私が数年前使っていた教科書には全く載っていませんでした。
ここ数年での糖尿病薬の新薬の登場は画期的であると感じます。
今回興味深いものを二つご紹介したいと思います。
まず一つ目に、最近主流であるインクレチン関連薬と呼ばれる薬です。
そもそもインクレチンって何でしょうか??
インクレチン(incretin)とは、インスリン(insulin)の分泌を促進する消化管 (intestine)のホルモン、INtestine seCRETion Insulin ということで名前がつけられました。
このホルモンは、食事摂取により、消化管から分泌され、膵臓のβ細胞のインスリン分泌を促進する作用を持っています。
この作用を利用したインクレチン関連薬が次々と開発されました。
インクレチン関連薬にも色々ございますが、ではどうやって薬の開発へとつながったのでしょうか?
面白いのが、エキセナチドという薬です。
この成分、なんと、もともとはアメリカ毒トカゲの唾液の分泌物から発見されました!
これが血糖降下作用を持つということが明らかとなり、これを人工合成することにより薬が開発されたのです。
毒トカゲの唾液から糖尿病の薬が生まれるだなんて誰が想像したでしょうか?
薬って何から生まれるか面白いですよね。
二つ目にご紹介したいのが今最も話題のSGLT2阻害薬という薬です。
そもそもSGLTとは、Sodium Glucose co-Transporter (ナトリウム・グルコース共輸送体) の略です。
腎臓の尿細管に存在するSGLT2を阻害することで、グルコースが再吸収されるのを防ぎ、血中のグルコース濃度を下げるという薬です。
ではどのようにしてこの薬は生まれたのでしょうか。
さかのぼりますと、はるか昔1835年、りんごの木の根(樹脂)からフロリジンという成分が発見されました。このフロリジンですが、後々、糖尿病動物において尿糖を誘発し、血糖を下げるということが報告されました。
ただこのフロリジンは、腎臓に存在するSGLT2だけでなく、小腸やその他全身に存在するSGLT1も阻害するため、薬としては実用化されませんでした。
ところがここ数年で、腎臓に選択的に存在するSGLT2のみを阻害すればいいのではないかと開発されたのが、選択的SGLT2阻害薬です。
これまでの糖尿病治療薬は膵臓に作用し、最終的にはインスリンを出すことで血糖コントロールを改善するものでした。SGLT2阻害薬の特徴は、腎臓に作用する薬であるということです。従来の糖尿病薬と異なり、膵β細胞に負担をかけない画期的な薬と言えます。
このように、最近めまぐるしく変化をとげる糖尿病治療薬の主な二つの薬が、動物や植物の意外なところからたまたま見つかり、それが新薬開発につながったというのは、非常に面白いことですよね。
今後も、どんなところから新しい薬が生まれるかわかりませんが、糖尿病薬のみならず画期的な新薬の開発に期待したいと思います!

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム