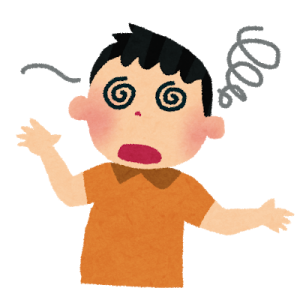薬の名前についているアルファベットのおはなし
2020年 7月 15日 水曜日
薬の名前には、語尾にアルファベットがついているものがあります。今回はこれらの意味を、例を挙げて紹介したいと思います。
1. 剤形を表しているもの
例1) メマリーOD錠など
ODはOrally Disintegrating(口腔内崩壊)の略で、唾液や少量の水で薬が溶ける工夫がされています。飲み込む力が弱くなったお年寄りでも飲みやすいこと、水が手元に無い時でも服用できることなど、利点が多くあります。
OD錠ではない通常のタイプの薬と同じように、水で飲んでも効き目に違いはありません。
例2) アダラートCR錠など
CRはControlled Release(放出制御)を意味します。徐放性製剤といって、薬が体の中で溶ける時間や場所を調整しているため、服用回数が少なくて済むのが大きなメリットです。本来1日3回飲まなくてはいけないところ、1日1回の服用で済めば楽ですよね。
CRの他にも、LA(Long Acting)やSR(Sustained Release)などといった表現で、徐放性を表しているものもあります。
このように工夫がされている薬を勝手に割ったり、かみ砕いたりして服用することは避けてください。本来複数回に分けて飲むはずの薬が一気に溶けだしてしまうので、副作用を起こす可能性が高くなってしまいます。
2. 成分に由来しているもの
例1) リンデロンVG軟膏
炎症を抑えるステロイド剤と、バイ菌を殺す抗生剤を配合した塗り薬です。有効成分のベタメタゾン吉草酸エステル(Betamethasone Valerate)とゲンタマイシン硫酸塩(Gentamicin Sulfate)が由来です。
例2) アスパラ–CA錠
カルシウムの補給に使われる薬です。Calcium……そのままでわかりやすいですね。
他にも、製造している会社の頭文字をとっているものもあります。例を挙げると切りがありません。
ご自身やご家族が飲んでいる薬の由来を調べてみると面白いかもしれませんね。

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム