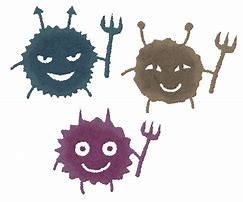こどもと「誤飲」のおはなし
2019年 3月 4日 月曜日
皆さんは子どもの誤飲でもっとも多いものは何だと思いますか?
誤飲ランキング
1位がタバコ(20.2%)
2位が医薬品・医薬部外品(14.8%)
3位がプラスチック製品(9.9%)
となっています。(厚生労働省 平成28年)
大半は1歳前後の乳幼児でおきていました。
床やテーブルの上など、子どもの手が届く場所に「タバコ」「医薬品」「医薬部外品」を放置しないように、こどもが立って手を伸ばしても届かない場所(1m以上高い場所)に置きましょう。
一番いいのはこどもの周囲にタバコを置かないことで,お母さんは妊娠がわかったら禁煙しましょう。
お父さんも妊娠がわかったら禁煙を考えてください。ご存知の通り、タバコの危険は誤飲だけではありません。
成分が体に吸収されることにより、それぞれの中毒症状が出てくる可能性があります。

タバコは食べにくく,タバコそのものを大量に飲み込むことはほとんどありませんが、タバコを誤って口に入れた場合、水などを飲ませるとニコチンが吸収されやすくなる恐れがあります。
飲み物を与えず、直ちに病院を受診するようにしましょう。

参考:厚生労働省報告書 2016年
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム