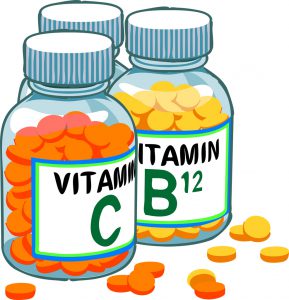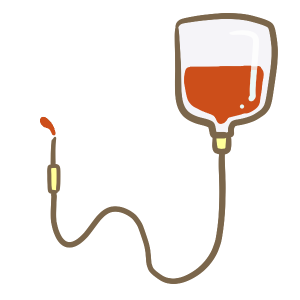肝臓のおはなし
2018年 10月 15日 月曜日
 今回は肝臓について少しお話しようと思います。
今回は肝臓について少しお話しようと思います。
皆様は肝臓についてどの様なイメージをお持ちでしょうか?
よく言われるのはアルコールと肝臓の関係性、これは一般的にもよく言われていますよね。

肝臓はヒトの体で最も大きい臓器です。
肝臓の主な働きは3つ。
- 体に必要な栄養素の合成・貯蔵
- 有害物質の解毒・分解(アルコールやお薬など)
- 食べ物の消化に必要な胆汁の合成・分泌
これらはどれも必要不可欠で、私達の生命維持に大きな役割を果たしてくれています。
そしてなんと、肝臓は唯一再生能力のある臓器です。
肝臓は少し切り取られてもまた再び同じ大きさの肝臓へ再生することができます。
85%が壊れても働き続けることができるといわれています。
不調でもなかなか不調を訴えてくることがない(症状として現れることがない)ので
『沈黙の臓器』や、『無口な働き者』といわれております。
そんな力強い肝臓ですが、不調が続くと元に戻らないこともあります。
肝臓にもいろいろな種類の病気と原因があるのですが、今回は肝臓の機能を維持するため、日頃から私達が気をつけることのできることを紹介します。
1.食べ過ぎない
→脂っこい食事や糖質のとりすぎは脂肪肝を招きます。特に果物の果糖は吸収がよく、肝臓で中性脂肪になりやすいため、注意が必要です。ごはん、パン、麺類は、ほんの一口残すだけで、1ヶ月に500g減量できると言われています。
2.飲み過ぎない
→お酒の飲みすぎは肝臓で中性脂肪が合成されやすくなります。
3.無理なダイエットによる栄養の偏りをなくす
→極端な食事制限など無理なダイエットをした人も「低栄養性脂肪肝」と呼ばれる脂肪肝になることがあります。
4.緑茶を飲むことを心がける
→緑茶に含まれるカテキンが体内、特に肝臓で発生する活性酸素を消去してくれるというデータがあります。メタボリック症候群にもいいという研究もあるので、脂肪肝予防にもなります。
5.適度な運動
→基礎代謝がアップすれば、太りにくい体質になりますので脂肪肝も予防できます。
特にスクワットやストレッチなどのインナーマッスルを鍛えることがより効果的です。逆に過度な運動は肝臓に負担をかけることもあるので、無理に激しい運動には注意しましょう。
6.加工食品を避ける
→加工食品に含まれる食品添加物は、体にとっては毒物です。肝臓で解毒されます。
また、加工食品は意外と塩分が多いため、塩分のとりすぎも防げます。
どうでしょうか。
少し意識していれば特別なことではないように思います。
これからは自分の肝臓、少しいたわってみてはどうでしょうか?

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム