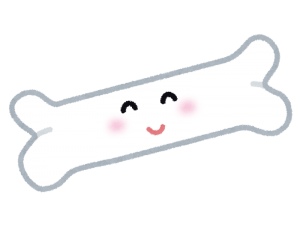お酒の強い味方のおはなし
2017年 12月 1日 金曜日
年末年始はお酒を飲む機会が増える時期です。
週末、平日関わらず飲み会がセッティングされる季節です。
なんなら朝まで連れてかれるようなケースもあるかも!?しれません。
お酒が好きなひとにとっては、お酒を飲む理由ができるステキな時期でもありますね。
お酒が好きか嫌いか、強いか弱いかはみなさまそれぞれ違いますが、いずれにせよ、二日酔いだけは避けたいものです。
翌日の仕事に響くのも困りものですし、充実した休日を失うのももったいないお話です。
そこで今回は二日酔いに効果があるとされる漢方薬をご紹介します。

【五苓散】
5種の生薬を含む漢方薬です。
この五苓散は主に利尿作用によって二日酔いの改善、予防を助けてくれるお薬です。
体内に入ったアルコールはアセトアルデヒドを経由して、最終的には水と二酸化炭素になって体の外へ出ていきます。そもそもなぜ人はお酒で散々楽しんだあとに、苦痛に見舞われるのかといいますと、この代謝の中間物質であるアセトアルデヒドが原因とされています。このアセトアルデヒドが頭の痛みや気持ち悪さを私たちにもたらします。
漢方薬の五苓散は利尿作用によってアセトアルデヒドの代謝された物質を体の外へ出す働きを助けてくれるお薬です。
この五苓散は第二類医薬品として市販もされているお薬です。
ドラッグストアなどで薬剤師、もしくは登録販売者のいる店舗で購入することができるので、比較的手軽に入手することもできます。
そして何より医療用医薬品としての五苓散の説明書、添付文書の効能・効果の欄にも「二日酔い」と記載のあるお薬です。
なお漢方薬は食間や食前、おなかの中が空の状態、空腹時の服用が効果的とされております。五苓散の用法用量にも例にもれず、食間か食前に使用するよう書かれております。

なお、市販されている五苓散の効能は以下の通りです。使用に際しては薬剤師や登録販売者とご相談するようにしてください。
体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹)のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
注)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。
もちろん、五苓散の力を借りても、症状を完全に抑えられるわけではありません。
翌日にお酒の影響を持ち越さないためには、くれぐれも飲みすぎないこと。長い時間飲み続けないように気をつけましょう。
また空腹時のアルコールは吸収が早くなるので、食事をとりながら飲むように心がけましょう。
飲みすぎてしまったなと思ったら、十分な睡眠と水分を取り、体をいたわってあげてください。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム