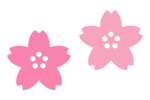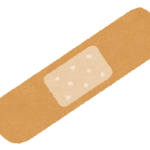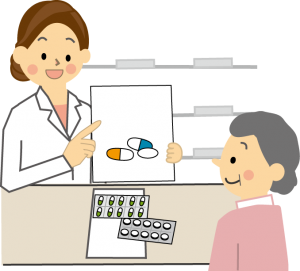気になる傷のケアのはなし
2016年 4月 1日 金曜日
街中でもカラフルで爽やかな色合いのお店が多くなって心が躍ります♪
春や夏にかけてはだんだんと薄着になりますよね。
半袖に袖を通して、ついつい気になるのが小さな切り傷や虫刺されなどの掻き傷、サンダルや履きなれない靴による靴づれだったりしませんか?
小さな傷でも跡は残したくないですよね。
そこで、最近、傷のケアで主流になってきた『モイストヒーリング療法』についてお話します♪
一昔前までは傷は消毒して、乾かし、かさぶたを作って治す考え方(ドライヒーリング)が主流でした。しかし、この方法だと消毒の時に沁みて痛みが出たり、傷跡が残りがちに。。。
ところが、最近では傷をしっかり覆い、患部の潤いを保ってキレイに治す湿潤療法(モイストヒーリング)の考えが広まってきています。
この療法は、細胞の成長や再生を促す成分が含まれる体液(傷口から出てくる透明な液体)を傷口に残し保つことで自然治癒力を高める効果があります。また、モイストヒーリングは消毒薬による傷口の殺菌は最小限に抑えることが推奨されています。消毒液が皮膚の再生に必要な働きを弱めることや、傷口の細胞を殺してしまう恐れがあるからです。
モイストヒーリングは正しい手順を踏めば、市販の絆創膏を活用して、家庭でも簡単に行うことが出来ちゃいます!!
~手順~
①水道水で傷口を洗う
→傷口にゴミやばい菌が残っていると感染の原因になるのでしっかり洗いましょう
②傷口を抑えて止血する
→洗浄後、出血が続く場合は清潔なタオルやティッシュペーパーなどで患部を押さえて止血します。火傷の場合は氷水で冷やして下さい。
③絆創膏で傷口を保護する素材(茶色の布製のものでなく、透明のポリマー製のもの)を貼って保護します。絆創膏には乾燥防止のほか、傷口を清潔に保ち、新たな傷を防ぐ効果もあります。
但し、出血がひどい場合や、深い傷、広い範囲のやけどなどは、病院での診察が必要ですので、異常を感じる場合は、医師に相談するようにしてください。
以前は医療現場で主に使われていた方法ですが、現在では傷口に合わせた大きさや貼り易いタイプの絆創膏が市販でも揃っています♪
夏が近付く前に薬局やドラックストアを覗いてみてはいかがでしょうか?
※参考資料
一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 ホームページ
http://www.jhpia.or.jp/product/bandage/bandage3.html
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム