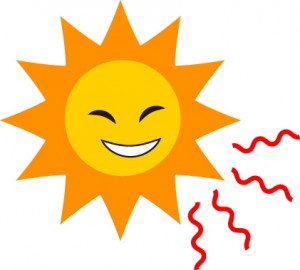からだによい油のはなし
2015年 8月 15日 土曜日
夏の間に強い日差しや冷たい空調にあたり、疲れが体に出てくる季節。夏バテ防止のために栄養価の高い食材をとろうと考えている方も少なくないのではないでしょうか。私がおすすめしたいのはスーパーフードです。
スーパーフードとは
●栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高い食品であること。
あるいは、ある一部の栄養・健康成分が突出して多く含まれる食品であること。
●一般的な食品とサプリメントの中間にくるような存在で、料理の食材としての用途と健康食品としての用途をあわせもつ。
と定義されています。
スーパーフードとそれに含まれている成分として、以下のようなものがあります。
スピルリナ(アミノ酸、ビタミン、ミネラル、食物繊維)、アサイー(アントシアニン:抗酸化作用)、ソバ(ルチン:ポリフェノールの一種で、抗酸化作用)、ブロッコリースーパースプラウト(スルフォラファン:デトックス効果) など
今回は特に、ふたつの「油」について、その主な栄養成分をご紹介します。
≪ココナッツオイル≫
以前から美容オイルとして全身のケアに用いられていますが、最近では料理に取り入れる人も増えてきてさらに注目を集めています。
・成分:
中鎖脂肪酸…60%が中鎖脂肪酸。体内で蓄積した脂肪を燃焼しながらエネルギーに変換されるため、「やせる油」とも呼ばれる
ビタミンE…抗酸化作用をもち、アンチエイジング、動脈硬化予防に関与
ラウリン酸…母乳に含まれる免疫成分。細菌の働きを抑える作用もあるのでカゼ予防にも良い
中鎖脂肪酸は熱に強いので200度までなら加熱調理をしても成分が壊れません。甘い香りがするので料理のアクセントやデザートに使用できます。普段使いの油をココナッツオイルに変更するだけで様々な効果が期待できそう。
≪アマニ油(フラックスシードオイル)≫
亜麻の種子から抽出した油。コレステロールを含まず、脂肪を分解して排出してくれる作用があるため、ダイエットサプリメントとしても服用されている。
・成分:
αリノレン酸…EPAやDHAと同じオメガ3系の脂肪酸で、必須不飽和脂肪酸のひとつ
抗アレルギー効果・高血圧予防効果がある
リグナン…ポリフェノールの一種で、女性ホルモンであるエストロゲンのように作用したり、またエストロゲンの分泌が多すぎるときは抑制して調整する作用があると言われている。
酸化しやすい油なので加熱調理は避けます。お好みのお酢や醤油等とあわせてドレッシングにしたり、スープやお味噌汁の香りつけに用いるとよいでしょう。
また、油とタンパク質をあわせた食材はリポプロテイン食材と呼ばれ、アマニ油と低脂肪のタンパク質を一緒に摂取することで消化・吸収がしやすくなると言われています。
油ときくとベタついて暑い日は避けたいイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、ご紹介したふたつはさらっとした口当たりで、非常に摂取しやすいもの。食生活に上手に油を組み込んで、栄養をしっかり摂って、疲れにくい体を目指してみませんか?
参考:日本スーパーフード協会 http://www.superfoods.or.jp/
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム