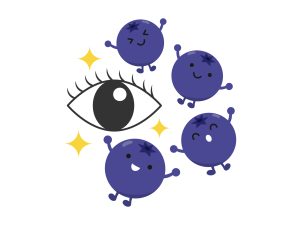秋の花粉症のはなし
2023年 9月 1日 金曜日
「花粉症」ときくと、スギやヒノキなどが原因で引き起こされる春の花粉症のイメージが強いですが、秋に花粉症になる人もいます。
「毎年秋になるとなぜか鼻水が出てくる!?」という方は、もしかすると秋の花粉症かもしれません。
秋の花粉症の特徴と対策について紹介します。

【原因となる花粉】
草本植物由来の花粉がメインです。
スギやヒノキといった木本植物の花粉に比べると飛散距離は数メートルとさほど長くありませんが、身近なところに存在しているため、知らない間に花粉を浴びてしまうおそれがあります。
原因として多いのは以下の植物の花粉です。
・カモガヤ(イネ科)
・ブタクサ(キク科)※日本で初めて報告された花粉症はブタクサ花粉症でした!
・ヨモギ(キク科)
・カナムグラ(アサ科)

【時期】
・花粉が飛散する期間は8月~10月。
・ピークは9月。
・地域によってはブタクサの花粉が12月頃まで飛ぶこともあります。
【症状】
秋の花粉症の代表的な症状は、春の花粉症と同様、何度も繰り返す「くしゃみ」、
透明でサラサラとした「鼻水」、呼吸が苦しい「鼻づまり」の3つです。

【対策】
春の花粉症対策に通ずるものが多いです。
<花粉に近づかない>
・公園や草原のほか、庭の雑草として生えることもあるので、
写真等で葉の形状などを記憶し、花が咲く前に除草する。
<家に花粉を入れない>
・花粉の付着しにくい素材(綿、ポリエステルなど凹凸の少ない生地)の服を着る。
・帰宅時に玄関前で花粉を払う。
<体内に花粉を入れない>
・マスクや花粉症用ゴーグルを着用する。
・帰宅後に洗顔、うがいをする。
・掃除を徹底する。
・空気清浄機を置く。

<正常な免疫機能を保つ>
・睡眠をよくとる。
・規則正しい生活習慣を身につける。
<鼻の粘膜を正常に保つ>
・飲酒、喫煙を控える。
・風邪をひかない。
【最後に】
以上、秋の花粉症について紹介しました。
風邪や通年性アレルギー性鼻炎との鑑別は難しいので、毎年決まった時期に鼻水やくしゃみ、のどの痛みなどの症状が出る人は、病院の受診やアレルギー検査をおすすめします。

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム