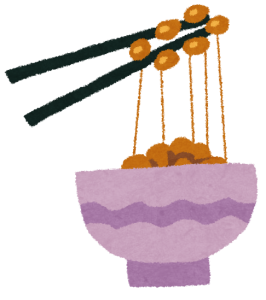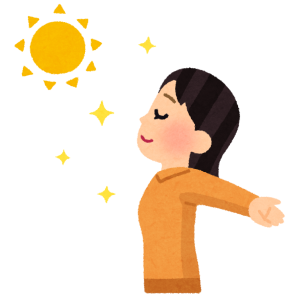脱水症状について
2023年 7月 15日 土曜日
暑くなってくるとテレビでも水分補給を促すものを見かけるようになってきます。
そこで今回は脱水症状についてお話ししたいと思います。
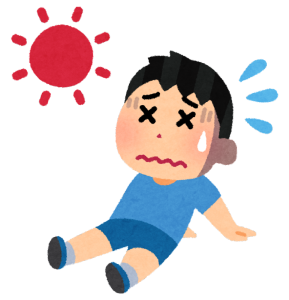
ヒトの体の全体重の約60%は水分でできているといわれています
(子供は70-80%、高齢者は約50%)
脱水症状は水分の摂取不足や体の中の水分が過剰に出て行ってしまうことで体の中の水分が不足し起こります。
また、脱水症状は体の中の水分だけでなくミネラルも不足している場合もあります。
症状としては、
・のどの渇き
・尿量の減少
・肌や口の中の乾燥
・頭痛
・まめい、たちくらみ
・吐き気など
といった症状が出ることがあります。
ひどい場合は意識障害などが起こることもあります。
脱水症状を起こさないためにもこまめに水分を摂ることを心掛けましょう。

ここで水分補給の注意点がいくつかあります。
・こまめに分けて摂る(一気に摂っても身体に吸収されずに尿として身体から出ていってしまいます)
・コーヒーやカフェインを含むお茶などは利尿作用があるので注意

また、汗をかいたときなどは経口補水液やスポーツ飲料などもうまく取り入れるといいですが、経口補水液は塩分などが多く含まれており、スポーツ飲料は糖分が多く含まれているので血圧が高めの方や血糖値が高い方などは摂りすぎに注意してください。
水分補給の目安として1日2.5リットルと言われています。
この水分は食事に含まれる水分も合わせた量なので、もし水分をそのまま摂るのが難しい場合はスープやお味噌汁など食事で水分を多めに取り入れるように意識してみてください。

最初でお話したように脱水症状と聞くと夏に起こると思う方が多いかと思いますが、冬にも起こる症状です。
季節に関係なくこまめに水分を摂ることを意識しましょう。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム