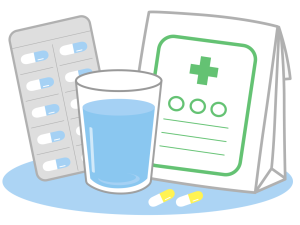漢方薬と西洋薬の違い
2023年 1月 15日 日曜日
皆さんは漢方薬をご服用されたことはありますか?
今では「風邪をひいたらいつも葛根湯をのむ!」という方がいらっしゃるくらい、
漢方薬が身近になりました。
今回は、漢方薬は西洋薬とはどう違うのかをお話していこうと思います。
漢方薬には、様々な効能を持つ複数の生薬が組み合わされています。![]()
生薬を組み合わせることで、より効果を増強したり、毒性を軽減するといわれており、
服用することで多くの症状に効果を発揮します。
人それぞれの体質や症状に合わせて生薬を配合しているため、
同じ症状の場合でも違う漢方薬が処方されることがあります。
一方、西洋薬は原則的に単一の成分でつくられています。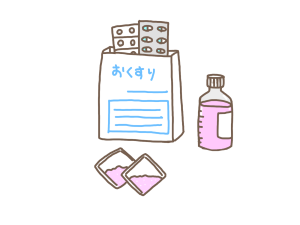
症状や病気に対して薬を選ぶため、その症状や病気をピンポイントに改善します。
即効性があるものが多いです。
具体例を挙げてみます。
風邪をひき、発熱や咳がでている場合だと、
西洋薬であれば、解熱薬、鎮咳薬や痰切りの薬、場合によっては抗菌薬など
複数の薬が処方されることが多いと思います。
市販薬であれば、複数の有効成分が入っているものもありますね。
漢方薬は、風邪のひきはじめなのか、慢性化しているのか、
咳は痰がからんだ咳なのか、乾いた咳なのか、汗が出ているかどうか、などの症状や
風邪になる前の、元々の体力はある方かどうかなどの体質から
処方する漢方薬を1つまたは2つ選びます。
風邪のひきはじめで発熱があり、元々の体力があった方であれば「葛根湯」、
発熱が高い場合は「麻黄湯」
風邪が治りかけているが、まだ微熱や咳が続いている場合は「麦門冬湯」
熱はかなり落ち着いているが体力が回復していない場合は「補中益気湯」
など、風邪症状にきく漢方薬はたくさんあります。
もし、ドラッグストアなどで薬の購入に迷われた際は薬剤師等にお気軽にご相談ください。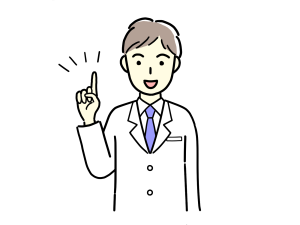
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム