夏風邪のおはなし
2019年 9月 1日 日曜日
外は暑くて、室内は冷房で寒い…夏風邪をひいてしまった方はいませんか?
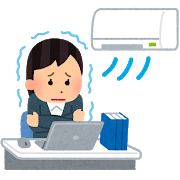
今回は、ドラッグストアで購入できる、のど風邪にオススメの漢方薬を2種類紹介します!
■その1
今や冷房なしには過ごせない日本の夏。
でも、冷房を使うと乾燥で声がカスカスになっちゃう…
そんな時におすすめなのが【麦門冬湯(バクモンドウトウ)】です!
?こんなとき使う
乾燥して声が枯れている
ケホケホと乾いた咳が出る
乾燥して痰が絡む感じがある
?おすすめする人
咳は止めたいが、口が乾いたり 眠くなる薬は使いたくない人
?おすすめしない人
痰がたくさんでる人
?入手するには
ドラッグストアで購入
病院で処方してもらう
【麦門冬(バクモンドウ)】という生薬が肺と喉に潤いを与えてくれます。
肺が潤うことで、乾いた咳や声のかすれ、乾燥による痰を和らげます。
潤いを与える薬なので、痰がたくさん出ている時に飲むと 痰がもっと出てしまうかもしれません?その場合はおすすめしません。
以前文献で、体の中で 声帯に水分が届くのは1番最後 と読んだことがあります。
ということは 声帯からは水分が抜けやすいし、潤いにくいということ。
漢方薬の中では 甘味があって飲みやすい味です。
眠くなる成分は入っていませんのでご安心を?
■その2
朝起きたら喉が痛くて 寒気はない、なんて症状の方にオススメの漢方薬は【銀翹散(ぎんぎょうさん)】です。
特に 喉からくる風邪のひき始めにぴったりです。
?おすすめする人
風邪のひき始めで喉の痛みが強い
寒気はしない
?おすすめしない人
寒気がする風邪
?入手するには
ドラッグストアで購入
銀翹散に入っている【金銀花(キンギンカ)】という生薬は頭部の炎症を抑える効果があります。喉の痛みや頭痛に良く効きます。 【連翹(レンギョウ)】には化膿止めの効果もあり 喉が腫れないようにしてくれます。
喉の痛みに効く【桔梗(キキョウ)】【甘草(カンゾウ)】も入っています。
銀翹散は体を冷やす効果が強いので、寒気がする風邪の場合は悪化させてしまうかもしれません。寒気がする風邪の場合は、葛根湯(カッコントウ)や麻黄湯(マオウトウ)がオススメです。
ドラッグストアで粉タイプと液体タイプが売っています。
液体タイプを冷蔵庫で冷やして喉に絡ませて飲む(=ガラガラうがいして飲み込む)のがオススメです。喉の熱をよく冷やしてくれます。
粉のままでももちろん効きます。
処方せんでもらえる薬ではないので、病院・調剤薬局ではもらえません。
味は少し苦味が強いです。連翹が苦いです。【薄荷(ハッカ)】も入っているので飲むとスーッと清涼感も感じられます。
「風邪かも?」と思ったその日にすぐドラッグストアで購入して薬を飲めば、病院にかかるよりも、お金も時間もかけずに治療できることもあります。
病院に行ったほうがいいか自分で判断がつかない時や、通院中・妊娠中の方は、ドラッグストアで薬剤師か登録販売者に相談してください。相談自体は無料ですのでお気軽に!

Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム



