ニンニクのおはなし
2018年 7月 15日 日曜日
夏が近づいてきて、どんどん暑くなってきましたね…!
みなさまいかがお過ごしでしょうか。 😮
夏バテにならないようにスタミナをつけたい時期ですね。
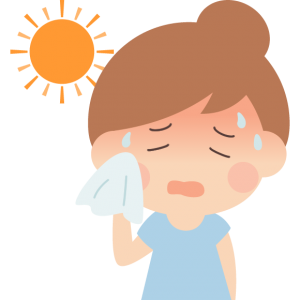
今回は、スタミナをつける食材の代表格「ニンニク」について
お話ししたいと思います。
ニンニクを食べるとスタミナがつく理由としては、
「アリシン」という成分が主に関与しているといわれています。
ニンニクに含まれるアリシンという成分が、ニンニクの細胞が壊れることで
酵素と反応しアリシンが発生します。
アリシンの疲労回復促進効果がニンニクを食べるとスタミナがつくといわれる
理由の一つです。
アリシンがビタミンB1と結合しアリチアミンという物質になります。
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換し、
乳酸などの疲労物質の蓄積を防止する栄養素です。
アリチアミンになることで、ビタミンB1の吸収を高め、
体内に長く保持するため疲労回復を促進するといわれています。
また、アリシンは抗菌作用による風邪予防や、
血行促進効果による動脈硬化の予防が期待されるといわれています。
アリシンは、加熱することにより、「スコルジニン」という成分になります。
スコルジニンは、アリシンと同様にビタミンB1と結合し
ビタミンB1の吸収を促進し、体内に長く保持する効果を持ちます。
加えて、スコルジニンには新陳代謝を促進し、
体内の毒素や老廃物を分解し排泄する作用があると言われています。
また、毛細血管を拡張し、動脈硬化を防止することで、
生活習慣病の予防にもつながると言われています。
ビタミンB1は、豚肉やレバー、豆類、米ぬか、玄米などの食材に
多く含まれていると言われています。
これらの食材とニンニクを合わせて食べることで、
より疲労回復につながるでしょう。
ニンニクとこれらの食材を食べて、夏を乗り切りましょう!!! 😛 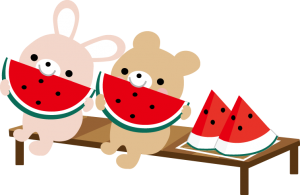
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム
 みなさんは
みなさんは



