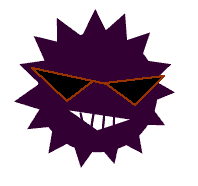12月も中旬になり、いよいよ年の瀬ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

一年で最も忙しい12月。年末で多忙になることに加え、寒い!感染症がはやっている!などが重なり、運動は二の次になりがちです。本日は、そんな状況でも便利な、自宅でほんの数分で出来る健康法「ラジオ体操」について取り上げてみます.
【いつでも、どこでも、だれでも】
ラジオ体操の歴史は、1928年に遡ります。当時、保険制度を学びに渡米した逓信省簡易保険局(現在のかんぽ生命)の幹部が、米国での取り組みを参考に、日本にも「放送経由の体操」の導入をはかったことがきっかけだったとのことです。当時も、「余裕の無い日常の中では、運動に多くの時間は割けないので短時間で出来るものを、また特別な設備や技術のいらないものでないと奨められません」(普及パンフレット)との普及方針でした。現在でも愛されている秘訣がこの辺にもありそうですね。
戦後、現在の形のラジオ体操第1は1951年、第2は1952に制定・放送が開始され、ご存知のように子供から大人まで、多くの人々に親しまれ続けています。
さらに1970年代には、大阪万博で「第9回1000万人ラジオ体操祭中央大会」が開催され、各国の注目を集めました。これをきっかけに現在でも世界各国でラジオ体操が愛好されているとのことです。
【特徴・効果について】
ラジオ体操の動きの特徴については、スポーツドクターの中村格子さんが著書で以下のようにまとめております。
・左右対称の動きを取り入れており、体の歪みを自然に解消。
・全身の筋肉、関節を満遍なく動かすことができる。
・ねじりや横曲げ運動で内蔵の動き、呼吸を活性化。
・約3分という無理なく続けられるコンパクトさ。
簡単な動きながら、どの筋肉を使うか?どの関節を伸ばすか?を意識することによって、より効果的に運動出来るとのこと。現在では、正しいラジオ体操を解説する情報も多数出版されております。知っていると思っている動きでも、改めて「どこを動かせば効果的か?」を思い浮かべながら実践するのも良いでしょう。
また、運動によるストレス解消、リフレッシュ効果も見逃せません。

【続けるコツは?】
そんなラジオ体操をうまく『活用して』いくコツは何でしょうか?
NPO法人 全国ラジオ体操連盟は、「一日どれくらい運動するのが健康にはよいか」との質問に、 厚生労働省の運動の目安を参考に挙げつつ、以下のアドバイスを示しています。
・即効性は期待せず、毎日続けること。
・無理はしすぎないこと。
細く長くでも、生活に取り入れることに意義があるのですね。
なお、現在では、音源も多様なものが入手可能です。従来のNHK音源のほかに、英語版のみならず、ご当地バージョン(山形弁、茨城弁、京都弁、鹿児島弁など)といったローカル版も登場しているとのこと。お好きな音源をチョイスすることで、より楽しんで体操できそうです。
【まとめ】
そもそも、病院での診察の後に受け取る医療用医薬品の中には、使い方の欄に「(『使用できる人の条件として』)ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る」と記述のある薬剤もあります。
適切な運動を続けることで、薬を飲まなくてよい確率を上げられるのなら、それに越したことはありませんね。
厚生労働省の調査によると、男性の70%、女性の75%は運動習慣を身につけていない状態とも言われています。生活に運動を取り入れるきっかけに、1日数分の「ラジオ体操」を始めてみるのはいかがでしょうか。

参考文献
1) NPO法人 全国ラジオ体操連盟 http://www.rajio-taiso.jp/index.htm
2) 厚生労働省発表「健康づくりのための運動基準2006」運動所要量・運動指針の策定検討会http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou02/pdf/data.pdf
3) 「新しい朝が来た ラジオ体操50年の歩み」財団法人簡易保険加入者協会 昭和54年発行
4)DVD付き もっとスゴイ!大人のラジオ体操決定版 中村格子・著