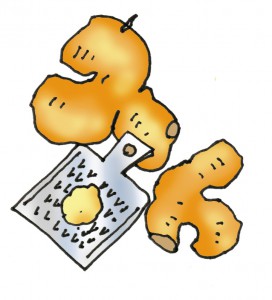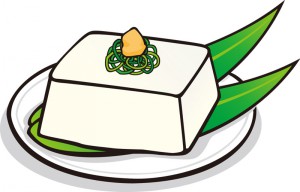脂質異常症のはなし
2015年 5月 15日 金曜日
桜の季節も過ぎ、暑さ感じる陽気も増えてきましたね。本日は、「脂質異常症」というものについてお話します。脂質異常症とは、血液中の脂質(LDLコレステロールや中性脂肪)が多すぎる病態のことです。未治療の場合、増えた脂質が血管内にたまり、動脈硬化になってしまいます。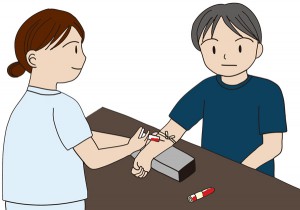
この時期はお仕事をはじめ、様々なものの節目となる事が多いかと思います。中には、健康診断を受ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、労働者の健康診断では、血液中の脂質の値が異常値を示す方が多いと言われています。少し古い情報になりますが、中性脂肪やコレステロールが高い脂質異常症の方は、潜在的な患者さんも含めると2,200万人にものぼるという報告があります。(平成12年厚生労働省循環器疾患基礎調査)
また、脂質異常症の診断基準の1つに「トリグリセリド(中性脂肪)」があります。以前に行われた国民健康・栄養調査では、トリグリセリドだけでみても、異常とされる基準値を上回る人は、以下のように報告されています。
●男性:30代から50代にかけて増加、50代ではおよそ2人に1人が異常値。
●女性:50代から増え始め60代でおよそ3人に1人が異常値。
脂質異常症という言葉を聞いた事が無い方も多いかと思いますが、実は私たちの身近に潜んでいる病態なのかもしれません。
なぜ、脂質異常症になってしまうのか。原因の多くは“食生活”にあると言われています。
LDL(悪玉)コレステロールが高くなる要因としては、
・肉や乳製品などの動物性脂肪の多い食品をよく食べる
・鶏卵や魚卵、レバーなどコレステロールを多く含む食品をよく食べる
・食べすぎによってカロリー過多になってしまう
以上のことが考えられます。
中性脂肪は、食べすぎ飲みすぎによる慢性的なカロリー過多が1番の原因とされています。
特に、お酒の飲みすぎは中性脂肪を増やしやすいため、注意が必要です。
以上のことから、脂質異常症を予防するためには“食事のコントロール”が必要になります。お肉や甘いものに偏らず、野菜も含めてバランスのよい食事が大切ですね。
(※中性脂肪が高い方は、砂糖に加え、果物などの糖質にも注意が必要です。)
これから行楽シーズンにさしかかり、BBQなど楽しいイベントも増えてくるかと思います。是非、食べすぎには注意して、野菜を取ることを意識して楽しんで下さいね。
参考資料:脂質異常症ホームページへ ようこそ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/seikatu/kousi/
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム