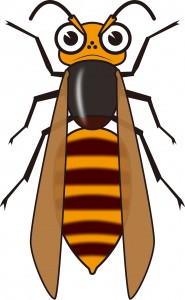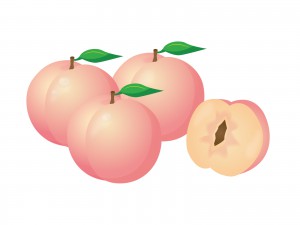紫外線と虫刺されのはなし
2015年 4月 1日 水曜日
日に日に気温が上がり、過ごしやすい時期となりました。
外で過ごす時間が長くなる方も多くいらっしゃると思います。
今回は外出時に気をつけたい紫外線と虫刺されの対策を中心にお伝えします。
<紫外線対策>
紫外線にはUV-AとUV-Bとの2種類があります
各々季節によって強さが変動します
UV-Aは初夏~秋、UV-Bは真夏の時期に強くなります
そろそろ紫外線対策を本格的に始める時期に入ります
具体的な対策方法としては、いくつかあります
●つばの長さが7cm以上の帽子
●衣服の工夫(綿とポリエステルの混紡で、綾織の衣服)
●UVカット加工がされているが色の濃くないサングラス
●日陰を利用する(午前10時から午後2時の陽射しの強い時間帯の屋外活動を避ける)
●日傘(光をカットし、かつ反射もする白色のもの)
●日焼け止め
なお、日焼け止めは以下に注意しましょう
●適切なSPFとPAのものを選ぶ→数値が高いものはお肌の負担になることもあるため、適切な数値のものをこまめに塗りなおすことが大事
●塗り残し、塗りむらを避け、重ね塗りする→量の目安:(顔の場合)クリーム状→真珠粒2個分、液状→500円硬貨1個分
●小児であっても、必ずしも子供用でなくて良い(健常な肌の場合)
<虫刺され対策>
クラゲやウミケムシなどの毒魚に刺された場合
1.パニックをおこさず落ち着き、海からあがる。場合によっては助けを呼ぶ。
2.とげや毛があれば取り除き、きれいな水で毒魚が触れた部位をよく洗う
3.アンモニア水や重曹水、抗ヒスタミン剤やステロイド剤を塗り、病院へ
ハチに刺された場合
1.近くに巣がある可能性があるため、現場から遠ざかる
2.毒を押し出す
3.流水で洗い、冷やす
4.抗ヒスタミン剤含有の副腎皮質ホルモン(ステロイド)軟膏があれば塗る
5.重症の場合は病院へ
適切な紫外線対策と虫刺され対策と準備を行って、夏のレジャーを楽しみましょう
<参考までに>
お肌に負担をかけてしまった場合は、季節に合ったお風呂でリラックスすることも大事です
4月・・・桜 (消炎、リフレッシュ)
5月・・・菖蒲 (血行促進、精神安定)
6月・・・ドクダミ (血管強化、抗菌・消炎)
7月・・・桃 (保温、消炎、収斂)
8月・・・薄荷 (保温、消炎・抗菌、清涼感)
9月・・・菊 (保温、血行促進、精神安定)
※排水口等に詰まらせないように、袋等に入れて使用しましょう
特に春先は環境が変わってストレスも溜まりがちです
日本ならではのお湯につかる文化をうまく取り入れて、快適な生活を健康でお過ごしください
☆参考書籍
知って防ごう有害紫外線(少年写真新聞社)/アウトドア救急ハンドブック(小学館)/お風呂大好き(生活情報センター)
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム