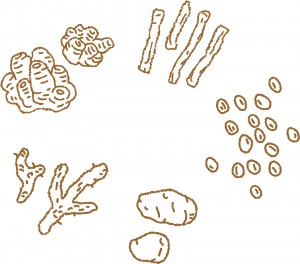くすりと食べ物のはなし
2015年 2月 15日 日曜日
これから日に日に春の陽気となり、心もはずんできますね。
今回はお酒を含めた飲食物とくすりのお話です。
まず、お酒でくすりを飲んではいけないことは、テレビなどを含め、かなり周知されてきていることと思います。ただ、くすりの中には、お酒では飲んではいなくても、お互いに影響を与えるものもあります。
・アルコールでくすりの働きが強く出る可能性があるもの
催眠鎮静剤・抗不安薬、精神神経用剤、糖尿病用剤、解熱鎮痛薬、抗てんかん薬など
・アルコールが分解されるのを抑えるので頭痛や嘔吐、顔面紅潮など不快な作用が出る可能性があるもの
一部の抗生物質製剤、一部の抗がん剤など
・アルコールで血圧低下などが起こる可能性のあるもの
狭心症治療薬など
また、お酒以外にも、コーヒー、紅茶、緑茶にはカフェインが多く含まれているので、やはり注意が必要なくすりもあります。
・カフェインの分解が抑えられ、イライラしたり不眠などが起こる可能性があるもの
抗うつ薬、抗不安薬、抗てんかん薬、催眠鎮静薬、一部の抗生物質など
・カフェインがくすりの体内代謝を抑える可能性のあるもの。
強心剤、気管支拡張剤など
・カフェインでくすりの濃度が上がり、鎮痛効果や出血傾向が強まる可能性があるもの
解熱鎮痛・抗血栓薬など
他にも、牛乳と飲むとくすりのはたらきが低下をしたり、副作用が現れやすくなるものもあります。
飲み物では、グレープフルーツジュースと飲むとくすりが強く効きすぎてしまったりするものもありますが、オレンジやレモン、みかんではそういったことが起こる可能性は低いと言われています。
食べ物では、納豆、緑黄色野菜、クロレラ、チーズ、マグロ、などで影響を受ける薬などもあります。
最近は口の中に入れると溶けて、水なしや少量の水、唾液等で飲みこむタイプのくすりも出ていますが、それ以外のくすりはコップ1杯程度のお水か白湯で飲むようにしましょう。
前述したすべてのくすりで起こるわけではありませんが、飲食物や健康食品などでの飲み合わせで心配なことがありましたら、医師や薬剤師に相談してみてはいかがでしょうか?
参考資料:くすりの適正使用協議会
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム