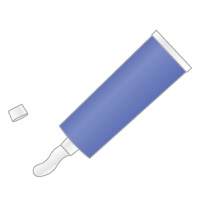添付文書に「塗擦」と記載がある場合、擦り込まないといけないのでしょうか。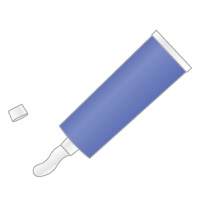
現在勤務している製薬メーカーの皮膚外用剤においては、擦り込む必要はないと回答していますが、製剤によって違いがあるのだろうかと疑問に思い、少し調べてみました。
日本薬剤師会編集の調剤指針には次のように記載されています。
『単純塗布法:最も広く行われている方法である。一般に軟膏剤を指腹などで患部に薄く伸ばす方法である。擦り込んで塗る方法を単純塗擦法といい、区別することがある。同じ量の軟膏を使用しても塗擦方法によって効果に大きな違いが見られることがある。』
本などを調べるうちに、2つの文献報告があることを知りました。
①ラットに1%インドメタシン軟膏を絆創膏に塗り貼った場合と10回、30回および60回単純塗擦した場合の4通りで、皮膚内および血中インドメタシン濃度を測定。塗布と塗擦の違いにより有意差があったとの結果。
②モルモットおよびラットにインドメタシンクリームを頻回塗擦(30回塗擦)した場合と単回塗布した場合の抗炎症・鎮痛作用を比較。頻回塗擦の方が、単回塗布に比較して効果が強く、また効果発現も早かったとの結果。
2番目の文献は全文を読んでいませんので詳細機序の記載があるかどうかは不明ですが、1番目の文献には「皮膚への塗布や塗擦行為が物理的刺激として反応に影響をおよぼすことが本研究からも考えられ…」と記載されていました。筋肉痛などに使用する皮膚外用剤では、マッサージ効果も期待できることから、塗擦することがあるようです。
「泥膏は酸化亜鉛の含有量が多く、粘稠度が高いため、容易には布に延ばせない。手に取って、よく練り合わせ、病変部にむしろ擦り込むように塗り延ばし、その上からパウターをはたいておく」と記載されている資料もありました。
逆に、アトピー性皮膚炎、乾癬、および褥瘡対策患者などでは刺激を与えないように塗布することが重要、ステロイド外用剤は患部に塗布する際に刺激を与えると痒みが発現するので、なるべく刺激を与えないように撫でるように塗布するといった情報がありました。
PmdaのHP上の医療用医薬品の添付文書情報検索ページで、用法用量の項目に「塗擦」と記載のある外皮用薬を検索すると156件、「塗布」と記載のある外皮用薬を検索すると752 件、「塗擦」と「塗布」の両方記載のある外皮用薬を検索すると54件の医薬品が見当たりました(2013年1月現在)。圧倒的に「塗布」が多いです。ステロイド外用剤で「塗擦」と記載されている添付文書があるのかどうか確認したところ、6件見当たりましたが、「塗布又は塗擦するか、あるいは無菌ガーゼ等にのばして貼付する。」との記載でした。アトピーに適応のある外皮用薬で塗擦と記載されている製品を検索したところ、全て尿素製剤でした。ただし、「塗布し、よくすり込む」と記載されている尿素軟膏もありました。
結局、それぞれの医薬品のメーカーの見解を確認するのが無難という結論に到りましたが、最近、新生児に対する「手あて」の効果が科学的に実証されたという記事を読んだばかりだったので、マッサージ効果や「手あて」の効果が気になるところです。
 記事は、医療者がNICU(新生児集中治療室)で過ごす赤ちゃんの全身を両手で包みこむ「手あて」を行ったところ、採血などの不快な刺激に対して増加する脳の血流が大幅に抑えられていたという内容でした。脳血流の増加が頻繁に起こることは、低出生体重児の脳の成長に影響を与え、脳容積の低下を招くリスクがあるだけでなく、発達障害との関連性も指摘されているそうです。
記事は、医療者がNICU(新生児集中治療室)で過ごす赤ちゃんの全身を両手で包みこむ「手あて」を行ったところ、採血などの不快な刺激に対して増加する脳の血流が大幅に抑えられていたという内容でした。脳血流の増加が頻繁に起こることは、低出生体重児の脳の成長に影響を与え、脳容積の低下を招くリスクがあるだけでなく、発達障害との関連性も指摘されているそうです。
娘達が幼いころ、ベビーヨガやベビーマッサージの教室で、赤ちゃんに触れること(タッチ等のスキンシップ)が大事とよく言われました。抱っこされて、心地よい思いを与えられると、赤ちゃんの脳内でオキシトシンと呼ばれるホルモンが産生され、グルココルチコイドの分泌を抑え、脳をストレスホルモンの影響から護ることが分かっているのだそうです。
マッサージ効果についても科学的なメカニズムの研究が増えてきているようです。両足を使う激しい運動後にマッサージを行うと、炎症性サイトカインの産生量が低減する等の変化があったことから、筋肉のダメージによる炎症がマッサージにより低減する可能性があるという内容の文献がありました。
参考文献
1)久木浩平:日薬理誌79,461-85(1982)「非ステロイド抗炎症薬の局所適応についての研究」
2)江藤義則他:薬理と治療16(2)791-5(1988)
3)日野治子:MB Derma82,6-12(2003)「特集/実践皮膚科外用療法マニュアル 古典的外用薬の使い方」
4)大谷道輝著:スキルアップのための皮膚外用剤Q&A(南山堂)
5)Honda N,et.al.:Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012 Jul 21.「Effect of therapeutic touch on brain activation of preterm infants in response to sensory punctate stimulus: a near-infrared spectroscopy-based study.」
6)Crane JD,et.al. Sci Transl Med 1 February 2012; Vol. 4, Issue 119, p119ra13「Massage therapy attenuates inflammatory signaling after exercise-induced muscle damage.」
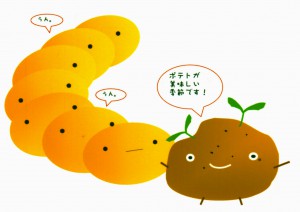 アクリルアミドの発がん性についてご存知でしょうか?
アクリルアミドの発がん性についてご存知でしょうか?