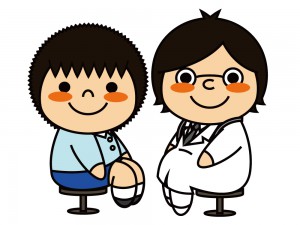喉にお箸を刺してしまったら?のはなし
2014年 11月 15日 土曜日
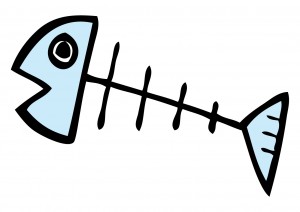 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では注意していても起こってしまうことがあるかな、と思い、実際に私の身内に起こった事例を取り上げてみました。
小さなお子様のいらっしゃるご家庭では注意していても起こってしまうことがあるかな、と思い、実際に私の身内に起こった事例を取り上げてみました。
先日、親類の3歳の女の子の喉にお箸が刺さって救急受診したという事件がありました。
お箸に限らず先の尖ったものは子供の手の届かない所に置いてあるらしいのですが、大人の真似をして自分で何でもやりたがる年頃なので、親の気づかないうちにお箸を手にして、何かの拍子に転んだようです。
幸いそれほど深く刺さっておらず、内視鏡でキズを確認後、経過観察となりました。
喉に異物が刺さった場合、ごく浅い刺し傷の場合は大きな問題はないようですが、深い場合、意識もはっきりしているからと言って刺入物は安易に抜いてはいけないようです。
病院での処置としては、キズを閉じた後抗生剤投与と経過観察で対応されるようです。
場合によってはCTで刺さったものの位置を確認後、内視鏡で刺したものを抜くという大掛かりな処置になるようです。
魚の骨を刺した場合でも要注意です。
いずれにしても、早めに医療機関を受診してキズの確認をしてもらいましょう。
(参考:学校内での事故や病気に対しての対応 出雲医師会)
http://www.izumo-med.or.jp/dl/member/safety/school_ermanu.pdf
【すぐに受診した方がよい時】
咽頭部の刺傷の場合は、刺傷分の確認・処置が困難なため、多くは早期受診が必要。
受診時には、刺したものを持参。破損のある場合には、同じもの(箸など)があれば持参。
☆口蓋扁桃外側深部に大血管があり、多量の出血は危険。
☆咽頭上方から斜め上方への深い刺入は、脳幹部損傷の危険。
特に、出血多量、呼吸障害、意識障害のある場合は救急車で搬送。
【魚骨異物】
小魚(アジ、ウナギなど)が原因で、痛み・嚥下困難がごく軽度の場合は下校後に受診でも可。痛み・嚥下困難がある場合は、早期受診。
比較的太い骨(タイ、サバなど)が原因の場合は、痛み・嚥下困難が軽度でも早期受診。
(参考:文献報告 副咽頭間隙に刺入した乳児箸異物例)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibirin1925/100/11/100_11_899/_pdf
小児では解剖学的に口腔から咽頭壁にかけて距離も大人に比較し短く、咽頭壁も脆弱なため内頸動脈閉塞症を発症する危険性が高い。内頸動脈閉塞症は内頸動脈が頸椎と異物の力で圧迫され動脈内膜が傷害されて生じ、受傷後48時間以内に発症することが多く、数々の神経症状を呈する。乳幼児の口腔内外傷や異物の症例で内頸動脈閉塞症が疑われる場合は必要に応じ入院し、 症状がなくても少なくとも受傷後48時間以内は神経症状や呼吸状態などの注意深い観察が必要と思われた。
Posted by pharmacist008.
カテゴリー: コラム